早起きの本質とは何か?
早起きは本当に必要なのか?
早起きが良いことだとされていますが、それって本当ですか? という話なんですよね。要は、早起きがすべての人にとってベストな選択かどうかは分からないわけです。例えば、夜型の人が無理に朝型に変えようとすると、生産性が落ちたり、体調を崩したりする可能性もありますよね。 この本では「15分ずつ早く寝て早く起きる」という方法を推奨していますが、そもそも早起きのメリットが万人に適用できるのかどうかが疑問です。 「朝は集中力が高まる」とか「夜のスマホをやめられる」といった話もありますが、それって単に「朝起きたから良い」んじゃなくて、「余計なことをしてないから良い」というだけの可能性もあるわけです。 なので、朝型生活が絶対に良いという前提で考えるのではなく、「自分に合ったリズムは何か?」を考えることが大事なのではないでしょうか。
15分早起きの効果は過大評価されていないか?
15分ずつ時間を前倒しすることで、無理なく早起きを習慣化できるというのが本書の主張です。ただ、ここで気になるのが「それって本当に効果があるのか?」という点です。 例えば、夜更かしが癖になっている人は、単に15分早く布団に入ったところで寝つけない可能性がありますよね。結局、スマホを触ったり、考えごとをしたりしてしまって、いつも通りの時間にしか眠れない、なんてこともあるわけです。 また、朝15分早く起きたからといって、その時間を有効活用できるかどうかは別の話ですよね。結局、二度寝してしまったり、ボーッとしているだけなら意味がない。 そう考えると、単に15分ずつ調整するよりも、「なぜ早起きができないのか?」という根本的な問題に向き合ったほうがいいんじゃないかと思うんですよね。
「早起き神話」の落とし穴
夜型人間はどうすればいいのか?
本書は「早起きができない人でも簡単にできる方法」として15分の調整を勧めています。でも、そもそも夜型の人にとっては、それが適しているのかどうかは疑問なんですよね。 遺伝的に夜型の人もいるので、そういう人が無理に朝型にシフトしようとすると、かえってパフォーマンスが落ちる可能性があります。 例えば、クリエイティブな仕事をしている人の中には、夜のほうが集中しやすいという人もいますよね。そういう人にとって、朝に無理やり起きることが本当に生産性を上げるのかどうかは微妙なところです。 要は、「早起きをすることで何を得られるのか?」という目的を明確にしないと、単に早起きすること自体が目的化してしまう可能性があるわけです。
「スマホをやめれば生産性が上がる」は本当か?
夜のスマホやSNSを控えることで、朝の時間を有効活用できるというのも本書の主張の一つですが、そもそも「スマホをやめれば生産性が上がる」という考え方自体が単純すぎるんじゃないですかね。 確かに、夜にダラダラスマホを触っていたら時間を無駄にしているかもしれません。でも、スマホを使うことで情報収集をしたり、リラックスしたりする時間が確保できている可能性もあるわけです。 つまり、スマホをやめること自体が良いのではなく、「どういう使い方をするか」が重要なんじゃないでしょうか。例えば、寝る前にSNSをダラダラ見るのではなく、オーディオブックを聴くとか、翌朝のスケジュールを整理するとか、もっと有意義な使い方があるわけです。 そう考えると、単純に「スマホをやめて早寝すればいい」という話ではなく、「時間をどう活用するか?」という視点が大事だと思うんですよね。
「朝の集中力」が活かせる人と活かせない人
朝に活動したほうが本当に効率がいいのか?
朝は脳がリフレッシュされているので集中力が高い、という話がありますよね。でも、それが誰にでも当てはまるかというと、そうでもないわけです。 例えば、低血圧の人や朝が苦手な人は、朝起きても頭がボーッとしていて、むしろ仕事の効率が落ちることもあるわけです。 また、朝に集中力が高いかどうかは、前日の睡眠の質にも左右されるんですよね。睡眠が浅かったり、夜中に何度も目が覚めたりすると、朝起きたときのパフォーマンスが下がる可能性がある。 なので、「朝は集中力が高いから重要な仕事をしよう」というのは、全員に当てはまるわけではなく、「自分にとって一番集中できる時間はいつか?」を把握することが重要なんじゃないかと思うんですよね。
「早起きの目的」を見失うと逆効果
本書では、「早起きをすることで好きなことに時間を使える」と言っていますが、それって本当にそうなんですかね? 例えば、「朝早く起きたけど特にやることがない」となったら、結局ダラダラしてしまうだけですよね。そうなると、「ただ眠いだけで意味のない早起き」になってしまう。 重要なのは、「何のために早起きをするのか?」という目的を明確にすることなんですよね。ただ「早起きすれば良いことがあるはず」と考えていると、途中で挫折する可能性が高い。 例えば、「朝の時間で英語の勉強をする」「運動習慣をつける」といった具体的な目標があるなら意味がありますが、単に「早起きすれば何か変わるかも」と思っているだけでは長続きしないわけです。 なので、早起きを習慣化する前に、「自分にとって必要な時間の使い方は何か?」を明確にしたほうがいいんじゃないかと思うんですよね。
早起きの「デメリット」に向き合う
早起きは本当に健康的なのか?
「早起き=健康に良い」という考え方がありますが、それって本当なんですかね? 例えば、睡眠時間を削ってまで早起きしようとすると、むしろ体に悪影響が出る可能性が高いんですよね。睡眠不足になると、集中力や記憶力が低下するだけでなく、免疫力が落ちたり、肥満になりやすくなったりする研究もあります。 本書では「今の睡眠時間をキープしたまま、徐々に早起きをする」という方法を勧めていますが、実際にはそう簡単に調整できるわけではないですよね。 例えば、普段12時に寝て7時に起きる人が11時45分に寝て6時45分に起きるとしても、「寝付きが悪い人」や「ストレスが溜まりやすい人」にとっては、その15分の差が意外と大きい。 「早起きが健康的」と言われる理由を深掘りすると、それは「規則正しい生活」が健康的なだけであって、単に「早起きすること」自体が健康に直結するわけじゃないんですよね。
睡眠の「質」を優先すべきでは?
結局のところ、重要なのは「早起きすること」ではなく「質の高い睡眠を確保すること」なんじゃないですかね。 例えば、同じ7時間睡眠でも、深くぐっすり眠れた7時間と、何度も目が覚める7時間では、体の回復度合いが全然違うんですよ。 そう考えると、「何時に寝るか?」よりも「どうやって良い睡眠を取るか?」にフォーカスしたほうが、健康にも生産性にも良い影響を与えるわけです。 この本でも「寝る前の環境を整える」とか「スマホを控える」といったアドバイスがありますが、結局のところ「眠りの質が悪い人」がそのまま早起きを目指しても、メリットよりデメリットのほうが大きい可能性があるんですよね。 なので、「まずは睡眠の質を改善すること」を優先すべきで、それができたうえで「早起きするかどうか」を考えたほうが、合理的なんじゃないでしょうか。
早起きで「得られるもの」と「失うもの」
朝に「余裕」ができるのは本当か?
「朝に余裕を持つことで、ゆったりとした時間を過ごせる」というのも、よく言われる早起きのメリットですよね。 でも、これって人によるんですよね。例えば、朝に余裕ができたとしても、その時間を有意義に使えなかったら意味がないわけです。 「とりあえず早起きしたけど、結局ダラダラしてしまう」「二度寝してしまう」という人にとっては、むしろ中途半端な早起きがストレスになる可能性もあるんですよね。 結局のところ、朝に時間を確保することが重要なのではなく、「その時間で何をするか?」が重要なわけで、早起きすること自体が目的になってしまうと、本末転倒になってしまうんですよ。
夜の「自由時間」が減るデメリット
早起きをすることで、当然ながら夜の自由時間が削られるわけですよね。 例えば、仕事終わりに映画を見たり、趣味の時間を楽しんだりしている人にとっては、「早く寝なきゃいけない」というプレッシャーがストレスになる可能性もあるんです。 「早寝早起きをしたせいで、趣味の時間が減ってストレスが溜まる」という状態になったら、本末転倒ですよね。 早起きをすることで何を得るのかだけでなく、「何を失うのか?」も考えないと、単なる自己満足になってしまうわけです。
「継続できる」方法が最優先
早起きよりも「習慣化」が大事
結局のところ、「早起きが良いかどうか」よりも、「どうやったら継続できるか?」のほうが重要なんじゃないかと思うんですよね。 例えば、早起きを習慣化するために、「毎日15分ずつ前倒しする」という方法が紹介されていますが、問題は「それを続けられるかどうか」なんですよ。 よくあるのが、「最初の1週間は頑張れたけど、その後リバウンドして元の生活に戻ってしまった」というパターン。 つまり、無理に早起きをしようとするよりも、「自分が自然に続けられるペースを見つける」ことのほうが、長期的には意味があるんですよね。
最適な「ライフスタイル」を見つけるべき
「早起きをしたほうがいいかどうか」は人によって違うわけです。 例えば、朝に強い人は早起きを習慣化することで生産性が上がるかもしれませんが、夜に集中できるタイプの人が無理に朝型にしようとすると、逆に効率が落ちる可能性もありますよね。 重要なのは、「一般的に良いとされること」を盲目的に信じるのではなく、「自分にとって最適なライフスタイルは何か?」を考えることなんじゃないかと思うんですよね。 この本の「15分ずつ調整する」という方法は、一つのアプローチとしては悪くないですが、全員に適用できるわけではない。 「なぜ自分は早起きしたいのか?」「それは本当に必要なのか?」を一度考えたうえで、自分に合ったリズムを作ることが、一番合理的なやり方なんじゃないでしょうか。

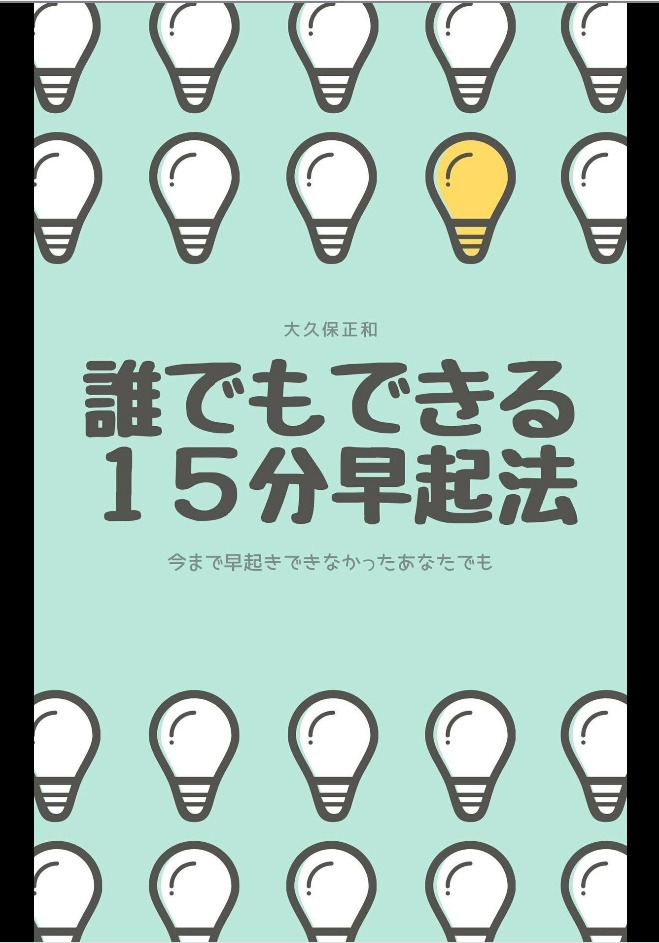


コメント