うーん、この本の内容を読むと、要は「判断力って大事ですよね」って話をめちゃくちゃ丁寧に解説してるんですけど、結局のところ、判断力ってそんな簡単に鍛えられるもんなんですかね? という疑問が出てくるんですよね。で、これをひろゆき視点で分析すると、まあ大体こんな感じになります。
判断力は訓練で身につくのか?
インバスケット思考は現実で通用するのか?
インバスケット思考って、要は「限られた時間内で優先順位を決めて、効率よく問題を解決しましょう」っていう訓練法なんですけど、これって実際に使えるのか? って話ですよね。確かに、管理職研修とかではよく出てくるんですけど、現場のリアルな環境では「シミュレーション通りにいかないことが多い」んですよ。
例えば、病院の院長が一時間以内に未処理案件をさばくっていう訓練をしても、実際の病院では患者の急変とか、スタッフのミスとか、予測不能なことが次々起こるんですよね。だから、「こういう訓練をすれば判断力がつく」と思ってる人って、ちょっと楽観的すぎるんじゃないかなと。
結局のところ、インバスケット思考で鍛えられるのは「机上の判断力」であって、「実践的な判断力」ではないんですよね。本当に判断力を鍛えたいなら、リアルな現場で実際に失敗して、その経験から学ぶ方が圧倒的に効率的なんじゃないかと思います。
10個の能力を身につけるのは非現実的?
この本では、判断力を鍛えるために「10個の能力」を活用しましょうって言ってるんですけど、正直、そんなに色々意識してる暇あるの? って話なんですよね。優先順位設定力とか、生産性とか、問題発見力とか、それぞれ単体で見れば重要なんですけど、同時に全部意識して動ける人ってどれくらいいるんですかね?
例えば、「優先順位設定力がないと、どうでもいい仕事に時間を取られて、大事なことができない」っていうのは分かるんですけど、現実問題として、優先順位を考える時間すらない状況もあるわけですよ。特に、仕事が忙しい人とか、突発的なトラブルが多い職場の人は、「優先順位を考える前にとにかく目の前の問題を片付けるしかない」って状況になりがちなんですよね。
で、これを解決するには、「10個の能力をバランスよく鍛えましょう!」っていうより、「1つか2つの能力に特化して、それを極めた方が早くない?」って思うわけです。例えば、優先順位を決めるのが苦手な人は「とにかく大事なことからやる」ってルールを決めるだけで、いちいち全部の能力を意識する必要がなくなるんですよね。
判断力を鍛えるにはどうすればいいのか?
判断のプロセスって本当に大事?
この本では、「判断は結果よりもプロセスが大事」って言ってるんですけど、それって本当ですか? って話なんですよね。例えば、経営者とかトップの意思決定を見てると、「プロセスなんか無視して、とにかく結果を出せ」って考え方の人が結構多いんですよ。
極端な話、プロセスがめちゃくちゃでも、結果が良ければそれでOKっていう世界もあるんですよね。例えば、アップルの創業者のスティーブ・ジョブズって、めちゃくちゃ独裁的な経営をしてたけど、結果的にiPhoneを生み出したわけで、そのプロセスが正しかったかどうかなんて、誰も気にしてないんですよ。
つまり、「判断のプロセスを丁寧にやりましょう」っていうのは、あくまで「普通の人向け」の話であって、結果を出せるならプロセスなんてどうでもいいって人もいるわけですよね。だから、プロセスを大事にするのは「失敗を減らしたい人向け」であって、「とにかく大成功したい人」には向いてない考え方なんじゃないかと思います。
意思決定力より「やるかどうか」の方が大事
この本では、「意思決定力が大事」って言ってるんですけど、実際のところ、一番大事なのって「決めること」じゃなくて、「やるかどうか」なんですよね。決断を下しても、それを実行しない人ってめちゃくちゃ多いんですよ。
例えば、「ダイエットしよう!」って決めるのは簡単なんですけど、実際に運動したり食事制限したりするのはめちゃくちゃ難しいじゃないですか。だから、本当に必要なのは「決める力」じゃなくて、「実行する力」なんですよね。
結局、「意思決定力を鍛えましょう!」って言われても、それよりも「決めたことをやり切る習慣を作りましょう!」って方が現実的なんじゃないかと思います。で、そのためには、「とりあえずやる」っていうクセをつけるのが一番手っ取り早いんですよね。
結局、判断力を鍛えるにはどうすればいいのか?
小さな判断を繰り返すのがベスト
この本の内容を見てると、「判断力を鍛えるには、フレームワークを学んで、それを実践しましょう」っていう感じなんですけど、実際のところ、一番効果的なのは「とにかく小さな判断を繰り返すこと」なんですよね。
例えば、「今日のランチは何を食べるか」とか、「どの電車に乗るか」とか、日常の中で小さな判断をどんどんしていくことで、自然と判断力って鍛えられるんですよ。逆に、普段から何も考えずに生きてる人が、いきなり「大事な決断をしましょう!」って言われても、うまくいくわけがないんですよね。
だから、まずは「細かい決断を意識する」っていうのが、判断力を鍛える上で一番現実的な方法なんじゃないかと思います。
判断力を鍛えるために実践すべきこと
優先順位を考える時間を減らす
前半では、「優先順位をつけることが大事だ」と言われても、実際にはそんな余裕がないことが多いという話をしましたよね。じゃあ、どうすればいいのかというと、「優先順位を考える時間を減らす」のが一番なんですよ。
例えば、アップルのスティーブ・ジョブズやメタ(旧フェイスブック)のマーク・ザッカーバーグは、毎日同じ服を着てるんですよね。これって、「服を選ぶ」という無駄な判断を省くことで、もっと重要な決断にエネルギーを使えるようにするためなんですよ。
同じように、仕事でも「重要なことは朝イチでやる」とか、「メールの返信は午後にまとめてやる」とか、ルールを決めちゃえば、いちいち考えなくて済むわけです。つまり、優先順位をつけるんじゃなくて、「最初から選択肢を減らしておく」っていう方が、判断力を鍛える上で合理的なんじゃないかと。
「判断の正しさ」にこだわりすぎない
本の中では「正しい判断をするためのプロセス」が重視されてるんですけど、そもそも「正しい判断」って何なんですかね? っていう話なんですよ。 例えば、株を買うときに「この会社は将来伸びる」と判断して投資しても、実際にはうまくいかないこともあるじゃないですか。でも、それは「判断が間違ってた」のか、「運が悪かった」のか、後にならないと分からないんですよね。
で、こういう話をすると、「だからこそ正しい判断をするために慎重に考えましょう!」っていう人が出てくるんですけど、慎重に考えても外れるときは外れるんですよ。だったら、「判断を間違えてもリカバリーできる仕組みを作る」方がよくないですか? って話なんですよね。
つまり、判断力を鍛えるっていうより、「間違えたときのダメージを最小限にする」ことの方が重要なんですよ。で、そのためには、いきなり大きな判断をしないで、小さく試してみることが大事なんですよね。例えば、新しいビジネスを始めるなら、最初から大金を投資するんじゃなくて、ちょっとだけ試してみて、うまくいくかどうか様子を見るとか。そういう「小さく始める習慣」をつける方が、結果的に判断ミスのリスクを減らせるんじゃないかと思います。
ヒューマンスキルは本当に必要なのか?
判断力とコミュニケーション能力は別物
この本では、「判断力を高めるにはヒューマンスキルが必要だ」って言ってるんですけど、それって本当ですかね? という疑問が出てくるんですよね。
例えば、世の中には「めちゃくちゃ仕事ができるけど、性格が最悪な人」って結構いるじゃないですか。でも、そういう人って意外と結果を出してたりするんですよ。逆に、「人当たりはいいけど、全然仕事ができない人」もいるわけで、ヒューマンスキルが高い=判断力が高いっていうわけじゃないんですよね。
要するに、「判断力」と「人にうまく伝える能力」って、そもそも別のスキルなんですよ。もちろん、両方持ってた方がいいのは分かるんですけど、「判断力を鍛えるためにヒューマンスキルを磨きましょう!」っていうのは、ちょっとズレてる気がするんですよね。
「お願いの仕方」で変わることもある
とはいえ、「言い方ひとつで結果が変わる」っていうのは事実なんですよね。例えば、同じ仕事を頼むにしても、「これやっといて」って言うのと、「忙しいところ申し訳ないけど、お願いできますか?」って言うのでは、相手の反応が全然違うんですよ。
結局のところ、判断力とは別に、「相手を動かす力」が必要な場面もあるわけで、そういう意味ではヒューマンスキルを身につけておくのは損ではないんですよね。ただ、それを「判断力の一部」として考えるのはちょっと違うんじゃないかなと。
判断力を鍛えるための具体的な方法
毎日「小さな決断」を増やす
前半でも話しましたけど、判断力を鍛えるには「小さな決断を増やす」ことが重要なんですよ。例えば、「今日のランチは何を食べるか」みたいな簡単なことでも、毎回「ちゃんと考えて決める」習慣をつけるだけで、判断力って勝手に鍛えられるんですよね。
よく「大きな決断をするためのトレーニング」とか言いますけど、大きな決断ってそんなに頻繁にあるわけじゃないんですよ。だから、日常の中で「意識的に小さな判断をする」ことを積み重ねる方が、実は効果的なんですよね。
判断ミスを減らすより、リカバリー力を鍛える
これも前半で触れましたけど、「判断を間違えないようにする」より、「間違えたときにどうするか」を考える方が現実的なんですよね。で、そのためには、「失敗してもすぐに立て直せる仕組み」を作っておくことが重要なんですよ。
例えば、投資をするときに「絶対に儲かる銘柄を見つけよう」とするより、「どの銘柄に投資しても、損を最小限にできる方法を考えよう」っていう方が、よっぽど確実なんですよね。ビジネスでも、完璧な判断をするより、「ダメだったら別の方法に切り替えられる」っていう仕組みを作る方が、結果的にうまくいくことが多いんですよ。
まとめ:判断力を鍛えるには「迷わないこと」が大事
この本では、「判断力を鍛えるには、インバスケット思考や10個の能力を活用しましょう!」って話がされてるんですけど、実際のところ、一番大事なのは「迷わないこと」なんですよね。
判断力が低い人って、結局「決めるのが遅い」んですよ。だから、最初から「選択肢を減らす」とか、「小さな判断を繰り返す」とか、「ミスをリカバリーできる仕組みを作る」っていうことをやった方が、現実的には効果的なんじゃないかと思います。
つまり、「考えるよりも、とにかく決めて動く」ことが、判断力を鍛える一番の近道なんじゃないですかね。

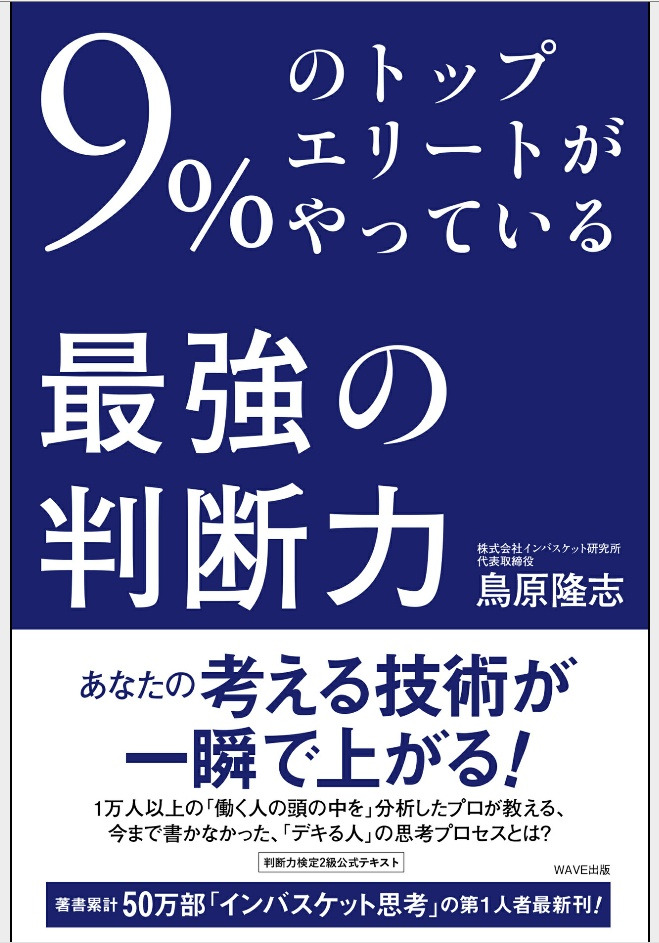


コメント