「太らない人」の裏側を論理的に見る
「夜中のラーメンは太る」という思い込み
まず、タイトルにある「なぜあの人は、夜中にラーメン食べても太らないのか?」という問いなんですけど、それって本当に「太らない人」が存在するのか?というところから始めた方がいいと思うんですよね。要は、夜中にラーメン食べても太らない人がいたとして、それって「特別な体質」とか「代謝がいいから」って言いたくなるんですけど、実際には翌日やその前後で帳尻を合わせてるだけだったりするわけです。
だから、こういうのって「太って見えないタイミングを作ってる人」が多いだけで、「ラーメンを食べても絶対に太らない魔法の体質」ってわけじゃないんですよ。結局、カロリーっていうのは、摂取と消費のバランスの問題で、夜にラーメンを食べようが、朝からドーナツ3個食べようが、総量が帳尻合えば変わらないんです。
レプチンの話はまあ、理にかなってる
レプチンっていう食欲を抑えるホルモンの話が出てくるんですけど、これは結構理にかなってると思うんですよね。よく噛んで、ゆっくり食べると満腹感が得られるって言われるけど、それって「満腹中枢に信号が届くまでに時間がかかる」っていう、まあ誰でも聞いたことあるやつです。
で、この「レプチンを活かす」っていう方法論って、言ってしまえば「自分を騙す方法」でもあるんですよね。つまり、お腹いっぱいになったと脳に思わせるのが先で、そのあとに実際の満腹がくるわけだから、先に脳をだますテクニックを使うと。で、そうやって食欲を減らすなら、実質的には「食べる量を減らす手段」なんだから、まあ効率的っちゃ効率的です。
「リセット法」はズルじゃなくて管理能力
食べたら調整する、それだけの話
「リセット法」っていうネーミングがちょっとズルく感じる人もいるかもしれないけど、要は「食べたら次で調整する」っていうだけの話です。これ、当たり前すぎて逆に驚くレベルなんですよね。飲み会で食べすぎたから次の日は控えめにするって、昔からよくある感覚ですし。
結局のところ、これは「自分の摂取カロリーを自覚できてるかどうか」って話なんです。現代人って、何食べたかよく覚えてなかったり、「まあ、いいか」で済ませちゃう人が多いから、こういう基本的なことをちゃんとやるだけでも差が出るって話なんですよね。つまり、体型って「意識の差」なんですよ。太らない人って、太らないように工夫してるだけ。
「1週間単位で見る」っていう視点の転換
ここで面白いのが、「1日単位じゃなくて1週間単位でカロリーを調整する」っていう考え方なんですけど、これって結構合理的なんですよね。普通の人って、「今日はラーメン食べたからダメだ」ってなるんですけど、そんな1日で人間の体って激変しないんですよ。
むしろ1週間単位で平均化することで、多少のズレが吸収できるわけで。つまり、長期的に見てバランスが取れてれば、1日単位の過ちって大した問題じゃないってことです。ここをちゃんと理解してる人って、長期的な視点を持ってる人なんですよ。で、こういう人ってダイエットだけじゃなくて、仕事とか人生設計もうまくいく傾向あるんですよね。
「太らない人」は意識してる人
「何を食べるか」じゃなくて「どう食べるか」
本書では「ベジファースト」とか「茶色い炭水化物」とか、いろいろ細かいテクニックが紹介されてるんですけど、要するに「どう食べるか」っていう話なんですよ。野菜を先に食べるとか、よく噛むとか、ゆっくり食べるとか、全部が「自分の体と食欲をうまくコントロールする」ための手段なんですよね。
逆に「何を食べるか」ばっかりに注目してる人って、制限が多くなりすぎて続かないんですよ。糖質制限だ、炭水化物抜きだ、って言ってると、食事がつまんなくなって、結局リバウンドするんです。だから「食べてもいいけど、工夫する」っていう方が、現実的だし継続できる方法なんですよね。
「間食も必要」っていう逆説的な論理
あと、「間食を取る方が太らない」って話もありますけど、これも一見すると逆説的に見えて、でもよく考えると理にかなってるんですよ。血糖値が急激に下がると、そのあと一気に上がりやすくなるんで、間食で血糖値を安定させておけば、過剰な食欲を防げるという。
つまり、「空腹を我慢しすぎない」っていうのがキモで、人間って我慢したあとに反動で食べすぎるんですよね。で、そういう反動が続くと、「今日はダメだったから明日から頑張ろう」とか言って結局続かない。だから「小さく食べて、爆発を防ぐ」っていう戦略の方が、実はうまくいくって話です。
睡眠と食事の関係性は、もっと注目されるべき
寝不足=太る、のシンプルな真理
睡眠と食欲のホルモンの話も、科学的にちゃんとデータがある話で、グレリンとレプチンのバランスが崩れると、食欲が暴走するっていう構造です。で、現代人ってスマホいじって寝不足になってる人が多いから、ここで太りやすい体質が出来上がってしまうんですよね。
つまり「夜更かしして太る」っていうのは、別に夜に食べたからじゃなくて、「寝なかったから」太った可能性もあるわけです。で、太った理由を食事のせいにしてる人って多いけど、実は生活習慣そのものに問題があるっていう。だから、本気で痩せたいなら「何時に寝てるか?」ってところから見直した方がいいわけです。
「痩せる努力」より「太らない環境作り」
で、最終的に言えるのは、「痩せようとする努力」って、実は無駄が多いんですよ。人間って意志力だけじゃどうにもならないことが多いんで、「痩せるんじゃなくて、太らない状況を作る」方が圧倒的に楽なんです。
たとえば、家にポテチ置かないとか、寝る前にスマホを手の届かないとこに置くとか、そういう環境のコントロールをした方が、最終的には習慣が変わるんですよね。つまり「頑張るんじゃなくて、頑張らなくても大丈夫な仕組みを作る」っていう考え方の方が、現実的で継続できるって話です。
食事管理は「メンタル管理」に直結している
体型管理よりも「心の安定」を重視した方がうまくいく
後半ではもうちょっと深掘りして、「なぜ食事に気をつけることが生活全体に影響するのか?」って話をしていきます。結局、食べ過ぎとか夜中のラーメンって、ストレス発散だったり、自分へのご褒美だったりするわけで、食事ってメンタルと直結してるんですよね。
だから「我慢して痩せる」っていうスタンスだと、結局ストレスが溜まって反動がくる。そうじゃなくて、「自分が気持ちよくいられる食事の仕方」を知ることの方が大事なんですよ。つまり、体型を維持するというより、精神的に安定している状態を作ることの方が、長い目で見れば結果的に体型も整う、という順番。
「食事=情報処理」として扱う視点
あと、あまり語られてない視点として「食事って情報処理なんじゃないか?」という考え方があります。たとえば、食事中にスマホいじったり、テレビ見ながら食べる人が多いんですけど、それって脳が「食べてる」という情報をちゃんと処理できなくなって、満足感が薄くなるんですよ。
つまり、脳が「食べた」と認識してないから、食欲が残る。で、結局また何か食べたくなってしまう。なので、「ちゃんと食べる」という行為を五感フル活用でやることが、実はダイエットに一番効くんじゃないかと思うわけです。これって、すごく当たり前のようで、なかなかやってない人が多いんですよね。
和食の基本「一汁三菜」は最強のフレームワーク
「何を食べたらいいか分からない人」はとりあえず和定食にしとけ
で、「一汁三菜」っていう日本の伝統的な食事スタイルが紹介されてますけど、これって実は最強のテンプレートなんですよ。要は、メインとサブのバランスが取れてて、野菜もあって、汁物もあって、炭水化物もあるっていう完璧な形。
現代人って、コンビニ飯とかジャンクフードで「手っ取り早く満腹になる」ことばっかり考えがちだけど、「満足感」っていうのは実はバランスで作られてるんですよね。栄養的な偏りがあると、どこかで物足りなくなる。だから、手間かけてでも定食を選ぶ人の方が、長期的には太らないっていうのは理にかなってます。
「牛丼より定食」が意味するもの
この中で紹介されてる「牛丼より和定食」っていう例が分かりやすいんですけど、要するに「炭水化物と脂質しかない食事」よりも、「いろんな要素がバランスよくある食事」の方が、脳も体も満足するって話なんですよ。
だから、時間がないとかコスパがどうとか言う前に、「自分の身体に対してどれくらい投資してるか?」って考えた方がよくて、安く早く済ませたものの代償って、結局あとで医療費とかメンタルの不安定さで返ってくるわけです。要は、安い食事には高い代償があるってことですね。
数字で管理することの効能
「体重を測るだけ」で自己管理が始まる
毎日体重を測ることが勧められてるんですが、これって「意識の可視化」なんですよ。つまり、自分の行動の結果を数字で見ることによって、「何をしたらどうなるか」がわかってくる。
体重が増えた=昨日食べすぎた。体重が減った=昨日セーブできた。こういう因果関係が見えるようになると、人間って勝手に行動を修正するんです。だから「見える化」ってすごく重要で、これって仕事のPDCAと一緒なんですよ。記録を取らないと改善もできないって話です。
「アプリを使って管理する」はめちゃくちゃ合理的
あと、アプリを使って記録するとか、レコーディングダイエット的な方法も紹介されてますけど、これは続けられる人にとってはめちゃくちゃ合理的。逆に言うと「記録を面倒くさいと感じる人は、太っても気にしない人」なんですよ。
人間って、自分に興味のないことには努力できないので、「体型を変えたい」と本気で思ってる人は、ちゃんと記録するんですよね。だから、毎日体重を測るとか、食べたものを書き出すっていうのは、自分に興味を持つってことの表れでもあるわけです。
「努力」の配分を変えると人生が変わる
運動よりも「考え方を変える方が早い」
よく「運動しなきゃ痩せない」とか言う人がいるんですけど、運動って効率悪いんですよ。30分走っても、ケーキ1個分くらいしか消費しない。だったら、最初からケーキ食べない方が早いんですよね。つまり、努力の配分を間違えてる人が多すぎる。
で、本書で紹介されてるのは「運動もしつつ、考え方を変える」というハイブリッド方式なんですよ。だから「運動だけして食事変えない」っていう人は、頑張っても結果が出にくいし、逆に「考え方と行動を少し変える」だけで体は変わる可能性が高い。
「太らない習慣」は資産になる
最終的には「太らない食べ方」っていうのは、一種のスキルであり、資産になるんですよね。誰かに教えることもできるし、自分の生活が安定する。要は、「人生の土台を支える技術」なんですよ。だから、「太らない」という結果そのものよりも、「どうやってそれを作ってるか?」っていうプロセスが大事。
たとえば、他人の食生活に口出しするんじゃなくて、「自分の習慣をちゃんと作る」。これって自己肯定感にも繋がるし、結果的にストレスが減る。そして、その余裕が他のことにも活かされる。つまり、痩せるっていうのは目的じゃなくて、余裕を生み出す手段なんです。

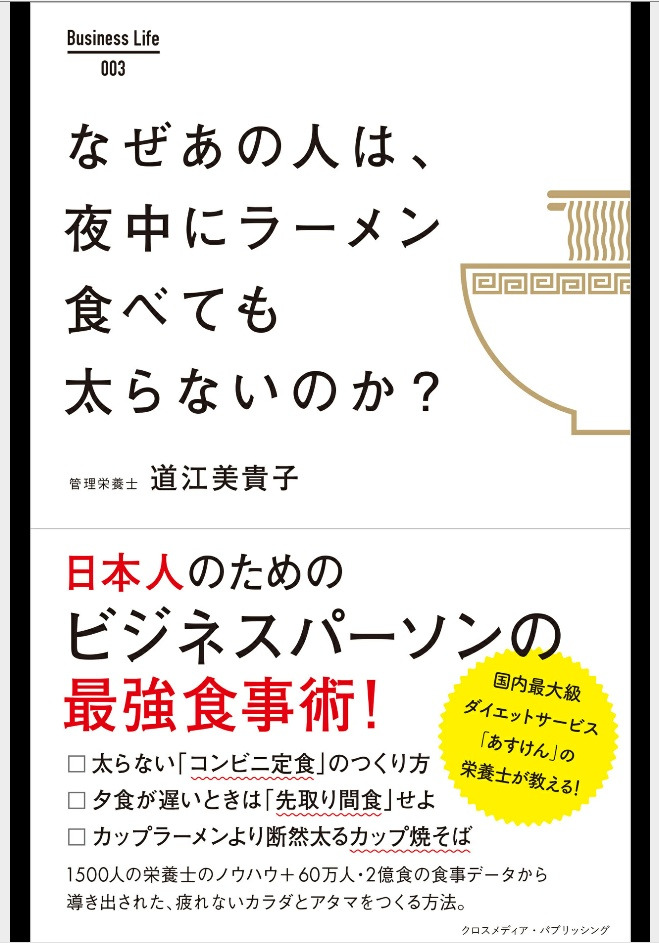


コメント