ホルモン信仰の落とし穴
ホルモンを信じすぎる人たちの心理
要はですね、「若さホルモンを増やせば太らない体が手に入る」って言うと、聞こえはいいんですよ。でも、冷静に考えると、ホルモンがすべての原因であり解決策であるっていう主張には、ちょっと無理があるんじゃないかと僕は思うんですよね。
結局、太るかどうかって、摂取カロリーと消費カロリーのバランスなんですよ。ホルモンの影響はもちろんあるにせよ、それが全てじゃない。なんでもかんでもホルモンのせいにするって、責任転嫁の一種だと思うんですよ。「アディポネクチンが少ないから太ったんです」って言えば、楽ですからね。
あと、副腎疲労とかDHEAの話もそうなんですけど、こういう体内のホルモンや臓器の働きに詳しくなると、なぜか自分の健康をコントロールできてる気になるんですよ。でも、それって実際には自己啓発的な幻想でしかない場合が多いんです。
実践できない理想論に意味はあるのか
本書では「豆腐とわかめの味噌汁を朝食に」「スクワットを毎日3分」「速歩を週3回」って、まぁ実践的なアドバイスも紹介されてますけど、それを毎日続けられる人がどれだけいるのか、って話ですよね。
人間って、基本的には怠け者なんですよ。だから、こんなに細かくルールを作ってしまうと、逆にプレッシャーになって続かないんですよね。「朝は豆腐を食べないとダメ」「夜に果物を食べたらアウト」って考えてたら、人生つまんなくなるんですよ。
で、たまにルールを破ったときに自己嫌悪になって、それがストレスになって、結局ホルモンのバランス崩すっていうね。つまり、健康のためのルールが健康を害する、という矛盾した現象が起きるんですよ。
健康ビジネスの仕組みを疑うべき理由
「若さ」や「健康」は売れるワード
「若さホルモン」「太らない体」「アンチエイジング」って、いかにもマーケティング向けのワードですよね。要は、こういう本が売れる理由って、「老い」や「肥満」に不安を持ってる人が多いからなんですよ。
冷静に考えてみてください。アディポネクチンっていう聞き慣れないホルモンを知ったからって、明日から健康になるわけじゃないですよね。でも、「今まで知らなかったすごい情報を手に入れた!」っていう自己満足が得られる。で、豆腐とかブロッコリーを買って食べて、ちょっと安心する。そういうサイクルで安心感を買ってるだけなんですよ。
だから、「こういうホルモンがあります」っていう事実を知るのは悪いことじゃないですけど、それで全てが解決するかのような売り方には、ちょっと引っかかるものがあります。
情報が多すぎて逆に混乱する問題
本書では、副腎疲労、アディポネクチン、DHEA、コルチゾール、基礎代謝、内臓脂肪、ビタミンC、ビタミンB群、水、果物の時間帯……って、いろんな要素が詰め込まれてますけど、これ全部意識して生活するのって無理ゲーですよね。
結局、知識が増えすぎると「何をしたらいいのかわからない」っていう状態になるんですよ。だから、多くの人が中途半端にやって終わる。
つまり、「多すぎる健康情報は逆に健康を害する」っていうパラドックスがあるわけです。情報は、使いこなせなければただのノイズですから。
根本的な問い:「若さ」とは何か
ホルモンで若返るという幻想
「DHEAを増やせば若返る」「アディポネクチンがあれば太らない」っていう話ですけど、じゃあそのホルモンが本当に若さを決めてるのかって、ちゃんと証明されてるの?って話ですよ。
要は、老化っていうのは複合的な現象で、ホルモンだけでどうこうできるもんじゃないんですよ。もちろん、一定の効果はあるかもしれない。でも、「それさえやればOK」みたいな単純化された言い方には、ちょっと違和感あります。
そして「若さ」っていうのも実は曖昧な概念で、人によって意味が違うんですよ。見た目の若さなのか、体力なのか、気持ちの問題なのか。ホルモンで測れる若さって、結局は一部でしかないんじゃないかなと思います。
なぜ人は若さに執着するのか
人間って基本的に「変わらないこと」を安心と捉える傾向があるんですよ。だから年を取るのが怖い。で、「若さを維持したい」っていう願望が生まれる。要するに、若さっていうのは「変化に対する恐怖」の裏返しでもあるんですよね。
でも、老いっていうのは自然な現象なんですよ。それを無理に逆らおうとすると、無理が出てくる。健康のための行動がストレスになって、逆に体に悪いことをしてるって、本末転倒ですよね。
だから、「若さを保つ方法」を考える前に、「なぜ若さにこだわるのか」っていう問いを自分に投げかけた方が、本質的には大事なんじゃないかと思います。
生活習慣の本当の問題点
努力よりも環境が大事という現実
健康本って「努力すれば結果が出る」とか「食事と運動を変えれば人生が変わる」みたいな話が多いんですけど、それって結局、個人の意思の強さに頼りすぎなんですよね。
つまり、努力で健康になれるっていうのは、ある意味で“きれいな嘘”なんです。現実には、仕事が忙しいとか、家庭の事情とか、そもそも運動する時間もない人が大半なんですよ。で、「できない自分が悪い」と思って自己嫌悪になる。この構造って、すごく非効率だと思うんですよね。
結局、継続できる仕組みを環境として用意しないと、健康習慣なんて維持できないわけで。たとえば「職場にエレベーターじゃなくて階段しかない」とか、「冷蔵庫にお菓子を入れないようにする」とか、そういう環境の方が人を変えるんですよ。
習慣化に必要なのは「意志」じゃない
毎日スクワットを3分する、ビタミンCを1000mg摂る、水を2リットル飲むって、こういうのって全部「意志の力」に頼った方法なんですよ。でも、人間の意志なんて基本的に弱いんですよ。僕も何度も意思でなんとかしようとして失敗してますから。
じゃあどうするかって言うと、「面倒くさいことをどうやってやらないで済むか」を考えるんですよね。たとえば、スクワットを意識しなくても、日常生活の中で自然に足腰を使うような環境にするとか。ウォーキングじゃなくて「駅まで徒歩20分」って場所に引っ越す方が効くんですよ。
つまり、意志に頼らずにやれる設計をするのが、本当の意味での健康術なんですよね。
情報リテラシーと健康
健康情報の「玉石混交」問題
今の時代、健康に関する情報ってネットに山ほど転がってるわけですけど、その大半は誰かが儲けるためのバイアスがかかってるんですよ。だから、本に書かれてる「推奨食材」や「サプリメントの量」も、実はメーカーの都合が入ってたりするんですよね。
それに、ホルモンの話って専門的すぎて、素人が判断しようがないんですよ。例えば「アディポネクチンが多いと痩せやすい」って言われても、それってどのくらいの数値なら多いのか、どうやって測るのか、そもそも市販の血液検査でわかるのか、って誰も説明してない。
だから、「これをすれば若返る」「これを食べれば痩せる」っていう断定的な情報って、いったん疑ってかかる方が健全なんですよ。
データの「解釈」を間違えないために
例えば「アディポネクチンが多い人は太りにくい」っていう研究があったとしても、それって「因果関係」じゃなくて「相関関係」なんですよ。つまり、アディポネクチンが高いから痩せてるんじゃなくて、痩せてる人はアディポネクチンが高い傾向がある、って話なんですよね。
こういう微妙な違いを無視して「アディポネクチンを増やせば痩せる」って言っちゃうのは、ちょっと科学的に無理がある。
だから、健康本を読むときって「これは仮説の一つだな」くらいのスタンスで読むのがちょうどいいんですよね。
「効率的な健康」のすすめ
最小の努力で最大の効果を狙う
「1%の努力」でも書いてますけど、僕は基本的に「最小の努力で最大の効果を狙う」っていうスタイルなんですよ。健康に関しても同じで、「全部やろう」とか「毎日完璧にこなそう」とかって、非効率すぎるんですよね。
だったら、「朝ご飯に豆腐を足すだけ」とか「夜の果物だけやめてみる」とか、そういう1個だけの工夫をまずやってみる方が継続性が高い。しかも、それで効果が出ればラッキーくらいの感覚でやるのがちょうどいい。
「やらない健康法」を決めることの大切さ
あとは、「何をやるか」よりも「何をやらないか」を決めるのも大事なんですよ。たとえば「夜にドカ食いしない」とか「SNSを見すぎて夜更かししない」とか。そういう“やらないこと”の方が、実は健康への影響が大きかったりするんです。
つまり、「足す健康法」じゃなくて「引く健康法」ですね。これって効率的で、精神的にも楽なんですよ。だって、「今日はやらなくていいことを1個減らせた」ってだけで成功体験になるんですから。
まとめ:ホルモンよりも「仕組み」と「視点」
結局のところ、「若さホルモン」や「DHEA」っていうのは、健康を考える上での一つの要素でしかないんですよ。重要なのは、ホルモンをどうこうすることじゃなくて、「どうすれば無理なく健康的な生活ができるか」っていう仕組みを作ることなんですよね。
そしてもうひとつ、「なぜ若さにこだわるのか?」っていう視点を持つこと。それがないと、ただの情報消費で終わってしまって、何も変わらないまま次の健康本を買ってるだけになっちゃいます。
だから、ホルモンの話も大事ですけど、それ以上に「自分の生活に合う方法か?」「続けられる仕組みがあるか?」っていう視点で考えることの方が、ずっと現実的だと思います。

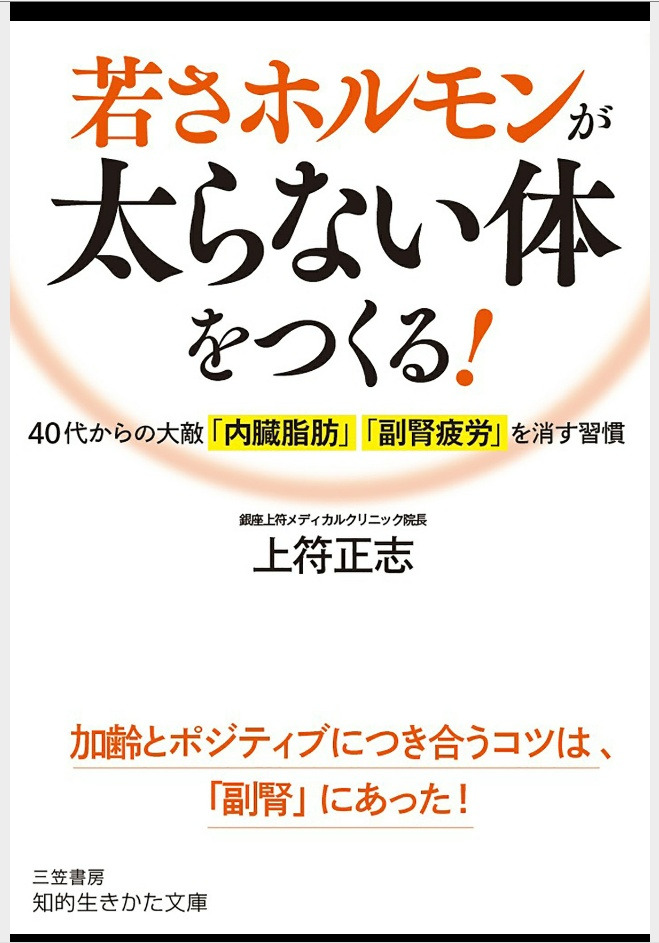
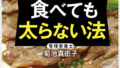

コメント