うーん、この本の内容をざっくり見ると「ビジネスの常識を疑って、全体最適を目指しましょう」って話ですよね。要は、目の前の問題だけを解決しようとすると、結局うまくいかないよってことを、いろんな事例を交えて説明してると。 まあ、こういう「常識を疑え!」系の話って、それ自体がもう常識になってる気がするんですけど、どうなんですかね? というわけで、ひろゆき視点でこの本を読み解いていきますね。
常識を疑えって、もう常識なんじゃないですか?
「全体最適」って言うけど、結局誰が最適なの?
本書の主張の一つに「部分最適ではなく、全体最適を目指せ!」というのがありますよね。でも、ここで気になるのは「全体」って誰のことを指してるの?って話なんですよ。 例えば、会社の利益を最適化するために、従業員の給料を下げるのが「全体最適」だと言われたら、それって労働者にとっては全然最適じゃないわけですよ。逆に、従業員の待遇を良くするために利益率を下げたら、株主にとっては「全体最適じゃない!」ってなるかもしれない。 つまり「全体最適」っていうのは、どこからの視点で見るかによって全然違うわけで、「全体を見ろ!」って言うだけだと結局あいまいな概念にしかならないんですよね。
ボトルネックを見つけるのは大事、でも…
本書では、ビジネスの効率を上げるために「ボトルネックを特定して改善しましょう」って話が出てきますよね。これ自体は正しいんですけど、現実問題としてボトルネックってそんな簡単に見つかるものじゃないんですよ。 例えば、ある工場で「この機械の処理速度が遅いから、生産性が落ちてる!」ってなったとしますよね。でも、実はその機械の処理速度を上げても、次の工程で人手が足りなくて結局ボトルネックが移動するだけだった…みたいな話ってよくあるわけです。 だから、本当にボトルネックを見つけるなら「仮説を立てて、試して、検証する」っていうサイクルを回し続ける必要があるんですよね。でも、多くの企業は「とりあえず目についた問題を改善して終わり!」ってやりがちなので、結局根本的な解決にはならないと。 要は、ボトルネックの管理ってそんなに単純な話じゃなくて、「1回見つけて改善したらOK!」みたいなノリでやってると痛い目を見るってことですね。
「よかれと思って」が失敗するのは当然
人間は長期的な視点を持てない
本書では「よかれと思ってやったことが逆効果になることがある」って話が出てきますけど、これって別に新しい話でもないし、人間の本能的に当たり前なんですよね。 例えば、ダイエットしようとして「食事を抜く!」ってやる人がいますけど、短期的には体重が落ちるけど、結局リバウンドするじゃないですか。これも「よかれと思って」が裏目に出る典型例ですよね。 で、ビジネスの世界でも同じことが起こると。例えば、社員のモチベーションを上げようとして「毎月の売上目標を達成したらボーナス!」って仕組みを作ったら、短期的にはやる気が出るけど、長期的には無理な売上を作るようになって、結果として会社全体の利益が下がるみたいな話。 こういう問題の根本にあるのは「人間は長期的な視点を持つのが苦手」ってことなんですよ。だから、ビジネスの世界でも「今だけ良くなる施策」をやって、結果的に失敗することが多いと。
そもそも「よかれと思って」って何?
あと、「よかれと思って」の話で気になるのは「誰にとっての良かれなの?」ってことですよね。 例えば、「この商品は絶対にお客さんのためになるから!」って思って新商品を開発したとしても、お客さんが本当にそれを求めてるかどうかは別の話じゃないですか。企業側は「お客さんのために」と思ってやってるけど、実際には押し付けになってることってよくありますよね。 結局のところ、「よかれと思ってやること」は、相手の視点に立って考えたつもりでも、実際には自己満足で終わるケースが多いんですよ。
「パラダイムシフト」を煽るビジネス書の罠
結局、パラダイムシフトって言いたいだけでは?
本書では「常識を疑い、新しい考え方にシフトすることが大事!」って話が出てきますけど、これってビジネス書あるあるなんですよね。要は、「今までのやり方はもう古い!これからはこう考えましょう!」って煽ることで、本を売ろうとしてるわけです。 でも、これってある種の心理トリックで、人間って「自分だけが新しい視点を手に入れた!」って思うと気持ちよくなるんですよ。だから、「パラダイムシフトしよう!」って言われると「確かに!これまでの考え方は間違ってた!」って思っちゃうんですけど、実際にはそんなに劇的な変化ってないんですよね。 例えば、10年前に「これからはSNSの時代!」って言われてたけど、今は「SNS疲れが問題になってます!」みたいになってたりするわけで、結局「時代が変わった!」って言われ続けるだけなんですよ。
変わらない本質を見抜く方が大事
で、「パラダイムシフト!」っていう話を聞くたびに思うのは、「でも、変わらない本質って何?」ってことなんですよね。 例えば、「ビジネスは顧客のニーズを満たすものだ」っていうのは、どんな時代でも変わらないわけです。SNSが流行ろうが、AIが発展しようが、「お客さんが欲しいものを提供する」っていう基本は変わらない。 だから、「新しい考え方を取り入れよう!」って言うよりも、「変わらない本質を理解しよう!」って話の方が大事なんですよね。でも、そういう地道な話って派手さがないから、ビジネス書ではあまり語られないと。
「在庫のジレンマ」に見る経営のリアル
在庫が多いとダメ、少なくてもダメ
本書では「在庫を持ちすぎるのも問題、少なすぎるのも問題」という話が出てきますけど、これって経営の難しさをよく表してますよね。 例えば、コンビニで「品切れをなくそう!」って在庫を増やしたら、売れ残りが出て廃棄コストが増えるし、「在庫を減らそう!」ってやると今度はお客さんが欲しい時に商品がないってことになると。 で、結局のところ「在庫を適正に管理する」っていうのが理想なんですけど、その「適正」が状況によって変わるから難しいんですよね。
結局、バランス感覚が大事
この「在庫のジレンマ」の話で言えるのは、結局「バランスが大事」ってことなんですよ。で、ここで面白いのは「バランスを取るのが一番難しい」ってことなんですよね。 例えば、会社の経営でも「社員の給料を上げたいけど、利益も確保したい」とか、「短期的な利益も欲しいけど、長期的な成長も考えたい」とか、どっちに振り切ってもダメだけど、ちょうどいいバランスを見つけるのが難しいと。 要は、「最適な答えがある」って思うと失敗するんですよね。どんな状況でも、ちょっとずつ調整しながらやっていくのが経営の本質なんじゃないかと。
「脱常識」が常識になった時代
「常識を疑え!」がビジネスになっている
本書のタイトルが『脱常識の儲かる仕組み』ってなってるんですけど、これって逆に言うと、「常識を疑え!」っていうのがビジネスになってるってことですよね。 最近のビジネス書って「今までのやり方はもうダメ!これからはこうしないと成功しない!」みたいなタイトルが多いじゃないですか。でも、こういうのを真に受けると、結局「また新しい非常識が出てくるんじゃないの?」っていう無限ループにハマるんですよね。 例えば、昔は「会社に忠誠を誓うのが当たり前!」って言われてたけど、今は「会社に縛られるな!個人で稼げ!」みたいな話になってる。でも、たぶん10年後には「やっぱり安定した会社員が最強!」みたいな話になってる可能性もあるわけで。
「新しい常識」より「自分に合うやり方」を探せ
だから、「新しい常識を取り入れよう!」っていうより、「自分に合うやり方を探そう」って考えた方がいいんですよね。 例えば、「これからは副業の時代だ!」って言われても、副業に向いてない人が無理にやったらストレスになるだけだし、「リモートワーク最高!」って言われても、対面の方が仕事がはかどる人もいるわけで。 結局、流行りの考え方をそのまま受け入れるんじゃなくて、「自分にとって最適なやり方は何か?」って考えるのが大事なんじゃないかと。
まとめ:「全体最適」とか言う前に、自分の最適を考えよう
この本の言ってることって、基本的には「全体最適を目指そう」とか「常識を疑おう」って話なんですけど、結局のところ、ビジネスってそんなに単純じゃないんですよね。 ・「全体最適」って誰の視点で見るかによって変わる ・「ボトルネックを見つける」のは簡単じゃない ・「よかれと思って」が裏目に出るのは当たり前 ・「パラダイムシフト!」って言う人ほど、シフトさせたいだけ ・「脱常識!」って言うこと自体が、もう常識になっている こういうことを考えると、大事なのは「流行りの考え方に流されないこと」なんですよね。 で、そのためには「自分にとって何が最適か?」を考える習慣をつけるのが一番重要なんじゃないかと。 というわけで、結論としては「全体最適を目指すより、まずは自分の最適を考えた方がいいんじゃないですか?」ってことですね。

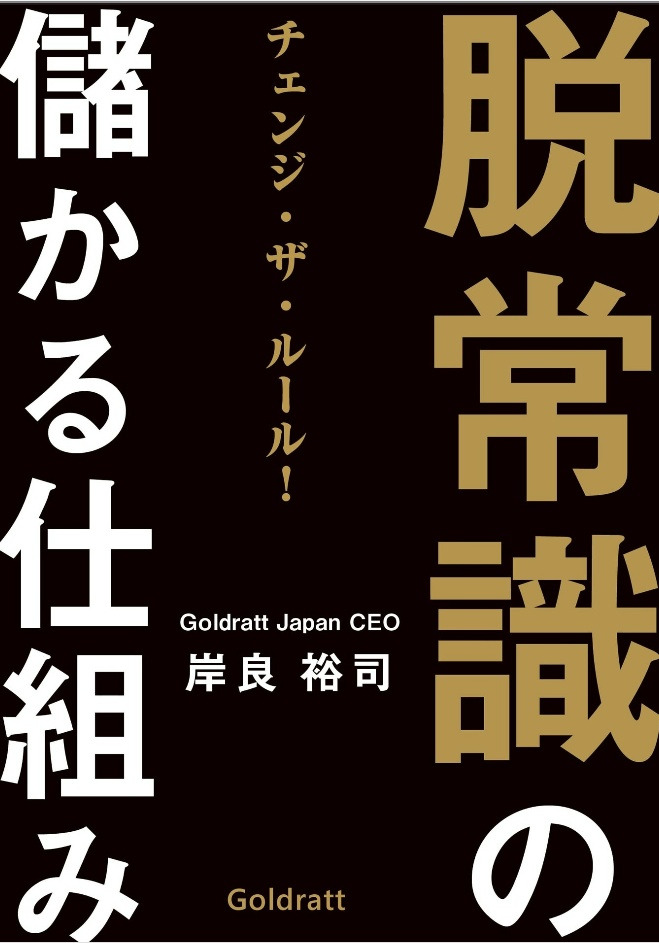


コメント