太らないカラダ作りって、そんなに難しくないんじゃない?
「2日間カロリーコントロール」の真実
要はですね、「食べ過ぎたら次の日ちょっと控えましょう」って話なんですけど、それって別に医学的な新発見でもなんでもなくて、普通に昔からある知恵なんですよね。日本人って「帳尻合わせ」の文化があるから、「今日は食べ過ぎたから明日は抜こう」とか、自然とやってたわけです。でもそれを今さら新しい理論っぽく出してくるのは、ちょっと違和感あります。
で、じゃあこれが有効かって話なんですけど、結局カロリーって1日で帳尻合わせるより、週単位とか月単位でバランス取った方がよくて、2日間でどうにかするっていうのは、短期的には意味あるけど長期的な視点がないですよね。しかも、食べ過ぎた日の翌日に絶食とかしちゃうと、逆にリバウンドしやすいっていうデータもあるんですよ。
だから、「2日間で調整すれば太らない」ってのは、まあ一部は正しいけど、過信しすぎると逆効果になりかねないです。人間ってそんな単純なカロリー計算機じゃないんで。
ながら運動って、効率いいようで非効率
本の中で「電車の中で腹筋を意識しましょう」とか「つり革持ちながらつま先立ちしましょう」とか紹介されてるんですけど、結局それって「意識しないとできないこと」なんですよ。つまり、継続するにはそれなりに気力が必要なんです。
僕が思うに、本当に効果的なのは「無意識でもできるレベルで習慣化された動き」であって、「意識しないとできない運動」ってのは長続きしないんですよね。たとえば、毎日自転車で通勤してる人が健康になるのって、意識してないけど運動してるからなんですよ。そこに「電車でつま先立ち」みたいな意識が入ると、逆に続かない。
あと、電車の中でつま先立ちとかしてる人を見たら、ちょっと不審者扱いされる可能性もあるわけで、そこまでして健康になりたいの?って話なんですよ。無理してやることって、長く続かないんですよね、結局。
「ガマンしない食事」って、実は一番むずかしい
「好きなもの食べていいけど、翌日に調整しようね」っていうのは一見合理的に見えるんですけど、そもそも我慢しないでコントロールできる人って、もうその時点で食に対してある程度の理性がある人なんですよ。
だから、本当に必要なのは「我慢しない方法」じゃなくて、「どうやって我慢する力を育てるか」なんですよ。ここがズレてる。僕はフランスで生活してるんですけど、フランス人って結構美食家なのに太ってない人が多い。それって、文化的に「一口ずつ味わう」とか「空腹を楽しむ」っていう感覚があって、無意識の中で食をコントロールしてるからなんですよ。
「我慢しない」っていうのは聞こえはいいけど、それって我慢できる人が言うセリフなんですよね。つまり、これって「すでにある程度できてる人向け」のノウハウであって、太りがちな人にはあまり有効じゃないんじゃないかなと。
健康のための「習慣」って、そもそも続けるのが前提なんですか?
習慣化って、そもそも人によって無理ゲー
この本では「習慣がすべて」みたいな書き方してるけど、それって結局「できる人はできるけど、できない人はできない」っていう当たり前の話なんですよ。で、それを「誰でもできます」っていうと詐欺に近い。
僕は、たとえば「朝起きたら水を3杯飲む」っていうのは、まあいいと思うんですよ。でもそれを毎日続けるのが難しい人もいて、そこを「根性でなんとかしろ」みたいに押しつけると、結局三日坊主になるんですよね。
習慣化って、「無理せず続けられるレベルから始める」のがコツなんだけど、この本では「まずはこれ全部やってみよう」みたいなテンションなんですよ。うん、それ無理だと思います。人間ってそんなに意志強くないし。
「ピンピンコロリ」って、実は矛盾してる欲望
「元気に長生きして、苦しまずに死にたい」って、そりゃ理想ではあるんですけど、そんな都合よくいくわけないじゃないですか。これって、言ってみれば「貯金しないで老後も豊かに過ごしたい」っていうのと同じくらいムシがいい話なんですよ。
ピンピンコロリを本気で目指すなら、それなりの準備とか、リスクの回避策が必要なんですけど、この本では「無理せず自然に健康に」っていう理想論に寄せすぎてるんですよね。要は、楽して長生きしたいって話なんですけど、それってたいてい実現しないです。
フランスだと、「老後に向けてどう死ぬか」っていうのを真面目に考える文化があって、「どう生きるか」よりも「どう死ぬか」が大事なんです。そういう視点がこの本には欠けていて、ただ「今を楽に生きながら長生きしたい」っていう、ちょっと自己中なメッセージに見えちゃうんですよね。
「健康的な生活」って、結局どこまで頑張ればいいんですか?
水を3リットル飲めって、本気で言ってます?
本の中で「1日3リットル水を飲みましょう」って書いてあるんですけど、これって結構しんどいですよね。トイレが近くなるのはもちろんなんですけど、普通にそんなに飲めない人も多いんですよ。で、「水を飲めば代謝が上がる」ってよく言われるけど、それって誤差の範囲だったりします。
つまり、1リットル飲んでた人が3リットルに増やしたら、多少代謝が上がるかもしれないけど、劇的に痩せるとかじゃないんですよ。むしろ、水を飲むのが苦痛になってストレスが溜まる方が健康に悪い。
あと、「水を飲めば痩せる」っていう幻想を与えることで、変に期待値が上がっちゃうのも問題で。現実としては、食生活と運動をトータルで見直さないと意味ないわけです。水だけでどうにかなるなら、もうとっくにみんな痩せてます。
「楽しく運動する」ってのは理想論じゃないですか?
「自分が楽しいと思える運動を続けましょう」って言うけど、運動を楽しいと感じる人ってそもそも健康リテラシーが高いんですよね。で、そういう人はこの本読まなくても勝手にやってる。
本当に必要なのは、「運動が嫌いな人でも続けられるような最低ラインの提案」であって、「あなたに合った楽しい運動を見つけよう」じゃないんですよ。たとえば、1日1回しゃがむとか、トイレに行くついでに背伸びするとか、そういうレベル感が大事なんです。
だから、「自分に合う運動を探す」ってのはある種の現実逃避で、探してる間にやらなくなるんですよ。楽しさって後からついてくるものであって、最初から楽しい運動なんて幻想です。
「会食でも無理しない」って、無理じゃないですか?
「会食ではサラダから食べましょう」とか「野菜を多めに頼みましょう」って書いてあるけど、そんな自由に注文できる環境ばかりじゃないんですよね。上司に焼肉屋連れていかれて「まずはキムチとサラダで」なんて言ったら、空気読めない奴って思われるわけで。
あと、「会食の翌日に調整」って言っても、そもそも毎日会食してるようなビジネスマンには無理な話なんですよ。そんなときに「自己責任で調整しろ」って言われても、それって努力しても報われない構造の中で個人だけが責任を負わされてる感じがして、なんかモヤモヤするんですよね。
社会構造の中で太りやすい人が生まれてるのに、そこを無視して「自分でコントロールしろ」って言うのは、ちょっと無責任じゃないかなと。
そもそも、「太らないカラダ」にそこまで価値あるんですか?
痩せてること=健康、って本当?
この本では「太らないこと=健康」って前提で話が進んでるけど、実際には痩せてても不健康な人っていっぱいいるんですよ。特に日本人ってBMIだけで健康判断しがちだけど、痩せ型の糖尿病とかもあるわけで。
で、「太らない」ことばかりにフォーカスすると、逆に健康より見た目重視の生活になっちゃう可能性があるんですよね。特に若い人は「体重が軽い=良いこと」って信じてるけど、それって不健康な価値観ですよ。
もっと言うと、「ちょっとぽっちゃりしてるけど元気な人」っていうのが一番健康的だったりもするんですよ。要は、数値や見た目に振り回されない生き方の方が、実は長生きに繋がる可能性が高い。
結局、「続けられること」が一番強い
健康法っていろいろあるけど、要は「何をやるか」より「どれだけ続けられるか」の方が大事なんですよ。で、この本の内容って、全部「やった方がいいこと」であって、「続けられる前提」で話が進んでるんですよね。
でも、現実としては「毎日水3リットル」「毎朝味噌汁と納豆」「階段使う」「つま先立ち」って、全部やるのは無理なんですよ。だから、本当に伝えるべきは「どれか1つだけ選んで、無理なくやろう」ってことなんじゃないかなと。
「健康的な習慣を全部取り入れる」んじゃなくて、「1個だけでも自分の習慣にできたらそれでOK」っていうメッセージの方が、よっぽどリアルだし、多くの人が救われると思うんですよね。
努力しない健康法の嘘
この本は「無理せず健康になれる」って言ってるけど、健康になるってある程度の努力が必要なんですよ。で、それを隠して「簡単ですよ」って言っちゃうと、逆に努力できない人を追い詰める結果になるんです。
たとえば、何やっても続かない人がこの本読んで「それでも無理だった」と思ったとき、「じゃあ自分はダメなんだ」と自己否定に入るわけですよ。でも実際は、この本の方法が万人向けじゃなかっただけなんですよね。
だから、必要なのは「努力しても続かないことは当たり前」っていう前提で、その上で「できる範囲で何か1つでもやってみよう」っていう緩さなんですよ。要は、「自己否定に繋がらない健康法」が、本当に人を救うんじゃないかなと思います。

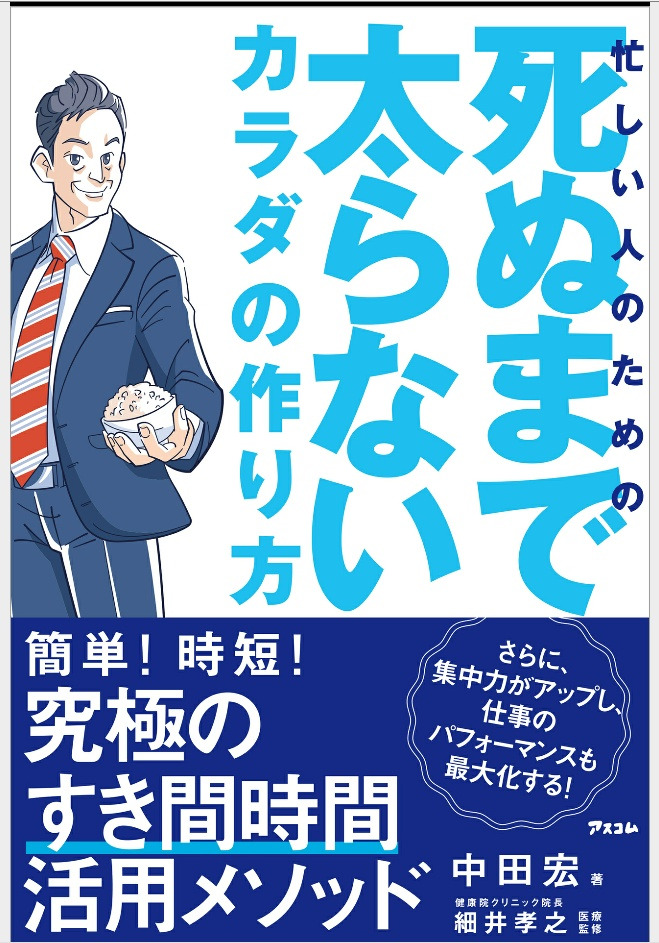


コメント