自分の「声」と向き合うことの意味
「声がコンプレックス」って、どうなんですか?
えーと、まず「声にコンプレックスがある」っていう人、多いと思うんですけど、そもそもそれって、誰かが「この声はダメだよね」って決めたわけじゃなくて、自分で勝手にそう思い込んでることが多いんですよね。たとえば、声が高い人が「子どもっぽい」って言われた経験があると、それだけでネガティブな印象を抱いてしまう。でも、現実的にはその声質が明るくて親しみやすいって評価されることもあるわけで。要は、自分の声をどう捉えるかの問題であって、実際の能力とか価値とはまったく別物なんですよ。
で、この本では「無理に声を変えるんじゃなくて、今の声を活かそうよ」って話をしてるんですけど、これってかなり合理的な考え方なんですよね。声帯って筋肉と似てて、ある程度トレーニングはできるけど、構造的に限界がある。だから、今ある素材をどう料理するかって発想のほうが効率がいいんです。努力の方向を間違えないっていう意味でも、すごく理にかなってると思います。
声のA面・B面って、結局「光と影」なんですよね
声質に「A面(強み)」と「B面(弱み)」があるっていうのも、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、それを意識的に言語化してるのは結構おもしろいです。たとえば「低くて渋い声」はリーダーシップを感じさせるけど、威圧感を与えることもある。逆に「明るくて高い声」は元気で親しみやすいけど、軽く見られたりうるさく感じられたりもする。
これってつまり、どんな特徴にもメリットとデメリットがあるってことで、要は「使い方次第」って話なんですよ。僕がよく言う「光が強ければ影も濃い」ってやつですね。だから、B面を否定するんじゃなくて、A面を意識して出しやすくするってのは、かなり戦略的なアプローチだと思います。
「声質診断」とは、自己認知のためのツールにすぎない
分類されると、安心する人って多いんですよ
声を8タイプに分類するっていうのも、正直な話、分類が好きな人にはウケると思います。人間って、自分がどこに属してるかを知ることで安心する生き物なんですよね。だから「あなたはパリピさんタイプです」って言われると、「ああ、自分はこう振る舞えばいいんだ」って安心する。でも、逆に「長老さんタイプ」とか言われて「え、地味ってこと?」って落ち込む人もいるわけで。
結局それって、レッテルをどう捉えるかって問題で、診断はあくまでスタート地点でしかないんですよね。そこからどう行動を変えるかが重要で、「あなたはこのタイプだからこうしましょう」っていうのは、正直ちょっと雑な処理なんじゃないかなって思います。
自分を変えるんじゃなくて「どう見せるか」
この本で一貫して言ってるのが「自分を変えるんじゃなくて、見せ方を工夫しようよ」って話なんですけど、僕はこの考え方にかなり共感します。だって、根本的な性質とか能力って、そう簡単に変えられないじゃないですか。むしろ、そのままの自分を「どういう形で他人に見せるか」のほうがコントロールしやすいし、結果も出やすい。
たとえば、声が通らない人が「発声練習を死ぬほど頑張る」よりも、「話すときに表情やジェスチャーで補う」とか、「話すスピードや間の取り方を変える」とか、そういう工夫のほうが効果的だったりするんですよ。つまり、無理に変わるんじゃなくて、「今の自分」をベースに最適化するって話です。
実用性と即効性、でも万能じゃない
録音して聞いてみるって、普通に合理的です
あと、地味に良いと思ったのが「自分の声を録音してチェックしよう」ってアドバイスですね。これ、たぶんやったことある人はわかると思うんですけど、初めて自分の録音聞いたときって「誰このキモい声?」ってなるんですよ。でも、それが現実で、他人はいつもその声を聞いてるんですよね。
だから、録音して客観的に自分の声を把握するってのは、すごく合理的なプロセスです。問題は「自分の声を嫌いになるかもしれない」って恐怖にどう向き合うかなんですけど、そこはもう「自分の声は他人のためのツールだ」と割り切ったほうがいい。要は「声のセルフブランディング」って話なんですよ。
「自己肯定感を持て」って、言うのは簡単なんですけど
この本の中で「自己肯定感を持とう」って話が何度か出てくるんですけど、僕はこれにちょっと懐疑的で。だって、自己肯定感って「持とう」と思って持てるもんじゃないじゃないですか。むしろ「成果が出た」とか「他人に褒められた」とか、そういう外的な要因が積み重なって、やっと芽生えるもので。
なので、「まずは自己肯定感を持ちましょう」って言われても、「いや、それができれば苦労しないでしょ」ってなるんですよね。だからこそ、「小さな成功体験を積み重ねる」っていう方が現実的なんじゃないかなと思います。声に限らず、なんでもそうですけど、自己肯定って「結果ありき」なんですよ。
場面に応じた声の戦略的運用
「どこで、誰に、何を伝えるか」がすべて
で、後半の話になるんですけど、「声ってどう活かすか?」の話は、実は「シチュエーションのコントロール」に尽きるんですよ。例えば、営業トークなら明るくハキハキした声が良いかもしれないけど、クレーム対応でテンション高く話すと火に油を注ぐことになる。つまり、声のA面B面って、結局「相手が誰か」と「どういう場か」によって変わるもので、絶対的な良し悪しは存在しないんですよね。
それを理解してる人って、実はそんなに多くない。場にそぐわない声のトーンで話して失敗する人って、「自分の声を活かす」っていうよりも、「相手に合わせる」って意識がないんですよ。要は、コミュニケーションってキャッチボールなんだから、自分の投げやすい球じゃなくて、相手が受け取りやすい球を投げろって話なんです。
「キメの一言」の威力って意外とすごい
それから面白かったのが、「就活の面接でぼそぼそ話す人でも、キメの一言を用意すれば印象が変わる」って事例なんですけど、これって要は「音量」や「声質」だけで勝負するんじゃなくて、「どこでどう魅せるか」がポイントなんですよね。
つまり、声が小さいのはある種の個性で、それを逆手に取って、ここぞという場面で「思い切って言い切る」ってやり方は、かなり戦略的。あえて普段は静かにしておいて、肝心なところで意志を見せる。ギャップを使うことで印象を残す。こういうテクニックって、声の強化じゃなくて、演出の話なんですよ。俳優がセリフの間を大事にするのと一緒で、「伝えたい部分だけ届ければいい」っていう割り切りができるかどうかが大事。
声の「生きづらさ」は社会構造の問題でもある
結局、「普通の声」って誰が決めたの?
で、ここまで読んでて思ったんですけど、「声にコンプレックスを持つ人が多い」ってのは、結局のところ「社会が求める声の基準」が画一的すぎるからなんですよね。明るくて元気な声が良い、落ち着いたトーンが信頼される、みたいな「正解の声」があるって前提が、そもそもおかしい。
この本はそこに真っ向から反論して、「いやいや、自分の声を活かせばいいんだよ」って言ってるわけで、これはある種のアンチ社会的規範の主張なんですよ。つまり、「適応じゃなくて、選択」なんです。自分を変えるんじゃなくて、自分に合った場を選んで活躍する。だから、コンプレックスを解消するには「声を直す」んじゃなくて、「自分を受け入れる社会」を見つけるって視点も必要なんじゃないかなと思います。
声とメンタルヘルスの関係、けっこう深いです
声の話って、実はメンタルとも直結してるんですよね。たとえば、緊張すると声が震える。逆に、自信があると声が自然と安定する。これって、声帯そのものよりも「心理的な安定感」の問題だったりするんですよ。で、本書が繰り返し強調してる「自己肯定感を持て」って話も、単なるメンタル論ではなくて、「声の出し方」としてかなり重要な要素なんです。
つまり、心の状態が声に出る。逆に言うと、声を整えることがメンタルにも影響を与える。だから、「呼吸法」や「腹式発声」が推奨されてるわけで、これって声の訓練というより、「心の安定」を作るためのトリガーでもあるんですよね。要は、声と心は双方向に影響し合ってるってことです。
話し方=演出と捉えるべき
ボイストレーニングより「編集」のほうが合理的
本書の主張に共感するのは、「無理に声を変えようとするのは時間のムダ」ってところですね。筋トレと一緒で、声もある程度はトレーニングできるけど、根本的に変わるには時間もコストもかかる。それより、今ある声の「編集作業」をするほうが圧倒的に合理的です。
文末でトーンを落とすとか、ゆっくり話すとか、接続詞に抑揚を入れるとか、そういう「編集」で聞き手の印象は大きく変わる。これはラジオの世界とかでよくある話で、内容は同じでも「話し方の編集」が違うだけで、まったく別物になるんですよ。要は、音声編集ソフトが使えない人ほど、自分の口で編集するしかないってことです。
「声は演出である」という視点が広まると楽になります
最後にまとめると、自分の声にコンプレックスを持っている人って、「声は自分のアイデンティティ」と思い込んでるんですけど、もっと軽く考えたほうがいいんですよね。声って単なるツールで、演出なんですよ。映画の演出と一緒で、「どう撮るか」次第で、同じ素材がまったく違って見える。
だから、自分の声を「演じるもの」として扱うだけで、心理的な負担はぐっと減ります。声を変えるのではなく、活かす。もっと言うと「演じるように話す」というスタンスに切り替えると、日常の会話もプレゼンもずいぶん楽になります。
この本の価値は、「声は変えられなくても、伝え方は変えられる」って視点をくれるところにあるんじゃないですかね。そういう意味では、声に悩んでる人にとってのひとつの武器になる本だと思います。

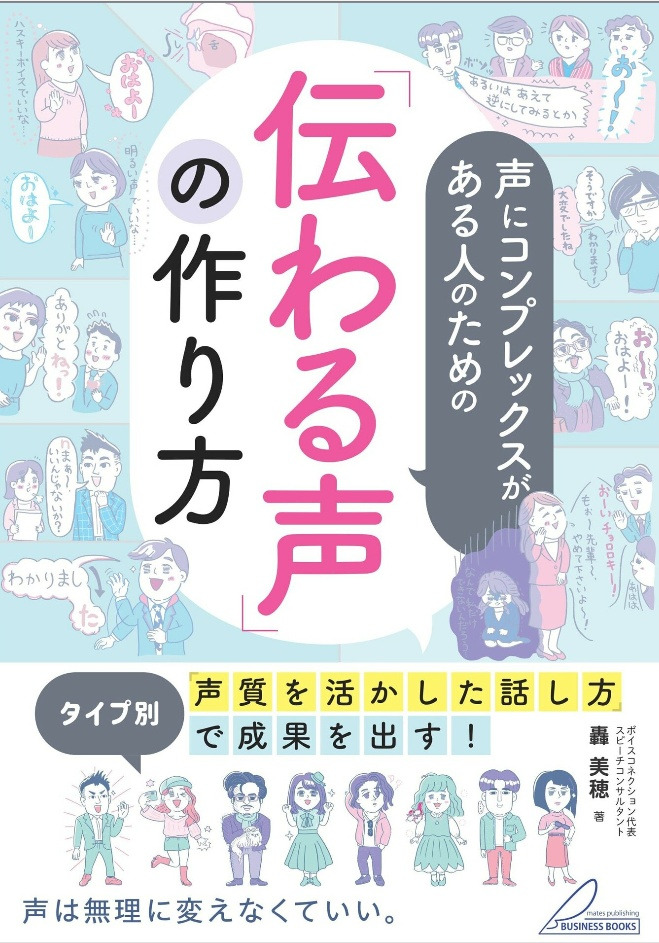


コメント