雑談力の本質と「知的さ」のギャップ
「教養がある=雑談が上手」は本当か?
要は、「教養がある人は雑談もうまい」って言ってるんですけど、それって本当にそうなんですか?って話なんですよね。確かに、知識が多ければ話題に困らないっていう側面はあると思います。でも、知識が多い人って、逆に相手がついて来れない話を延々としちゃうこともあるんですよ。
例えば、哲学とか歴史とか、めちゃくちゃ詳しい人がそれを熱く語っても、相手が興味なければそれってただの自己満なんですよね。だから、「教養がある=雑談がうまい」っていうのはちょっと短絡的すぎて、むしろ「相手に合わせて話題を選べる人がうまい」って話の方が本質に近いと思うんです。
あと、「教養」っていう言葉自体があいまいで、人によって定義が違うんですよ。アニメに詳しいのも、アイドルに詳しいのも、広義の教養ですし。だから、雑談力を「教養」って言葉でくくるのは、ちょっと雑だなって思います。
共感で信頼関係が生まれる…って、それ営業トークじゃない?
「共感されるテーマで話すことで、信頼関係が生まれる」って書いてあるんですけど、これってよくある営業マニュアルと同じなんですよね。営業って、相手の趣味とか興味を探って、「あ、僕もそれ好きなんですよ!」って共感を演出するのが基本なんですよ。
でも、それって本当に「信頼関係」なんですかね?共感っていうのは、本当にそう思ってないと薄っぺらくなるし、相手にもバレるんですよ。だから、「共感しよう」と思って無理に合わせるくらいなら、「あ、それ僕は興味ないですけど、なんでそれが好きなんですか?」って聞いた方がよっぽど誠実だし、会話も盛り上がるんですよね。
つまり、共感を前提にした会話って、場合によっては相手に媚びてるだけになっちゃうんで、それが信頼に繋がるとは限らないんですよ。
会話のテクニックが「雑談力」だという勘違い
質問力って「技術」じゃなくて「興味」なんじゃない?
「質問力が大事」って書いてあるんですけど、そもそも質問って、技術でやるもんじゃないと思うんですよ。相手に興味があったら、自然と質問って出てくるじゃないですか。「最近何か面白いことありました?」って聞くのも、それを聞きたいから聞くわけで、マニュアル的に聞くもんじゃないんですよ。
要するに、「質問をしよう」っていう姿勢がある時点で、もう興味がないってバレちゃうんですよね。会話って、自然体であることが一番大事で、「テクニックで盛り上げよう」って考え始めた時点で、雑談じゃなくてプレゼンになっちゃうんですよ。
だから、「質問力」っていうより、「相手に本当に興味を持つこと」の方が大事で、それって別に教科書で学ぶもんじゃなくて、生き方とか性格の問題だったりするんですよね。
リアクションって、そんなに重要ですか?
「それはすごいですね!」みたいなリアクションが大事って話なんですけど、それも結局、「うまく雑談してる自分」になろうとしてるだけなんですよ。そんなに相手の話、すごいって思ってないのに、「すごいですね!」って言うのって、むしろ失礼じゃないですか?
リアクションって、相手に合わせるための演技になってしまうと、それってもう雑談じゃなくて演劇なんですよね。演技しながら話すのって、疲れるじゃないですか。だから、自然な反応をしてればそれでいいんですよ。驚いたら驚くし、つまらなかったら「へぇ」で終わればいい。
雑談って、無理に盛り上げる必要ないんですよ。沈黙も会話の一部だし、無理に間を埋めようとする人って、逆に話しにくいこと多いんですよね。
「失敗談で安心感」ってホントに効く?
笑える失敗談がある人はいいけど、ない人は?
「失敗を共有すると相手が安心する」っていうのも、よくある話なんですけど、それって失敗談がネタになるくらい軽いものだから成立するんですよ。ブラック企業でうつになった話とか、いじめられて引きこもった話とか、そういう重いやつは雑談では出せないし、出したら空気が凍るんですよ。
要は、笑える失敗談が言える人って、それ自体が一種の才能であって、「失敗談を出せばいい」っていう簡単な話じゃないんですよね。それに、笑いを取れるってことは、その人がある程度コミュ力あるってことだし。
だから、「失敗談を共有しよう」っていうアドバイスは、一見優しそうに見えて、実はハードル高いんですよ。だって、自分の失敗をネタにして笑いを取れるだけの余裕が必要なんですから。
「自分を下げる」って、ただのセルフブランディングじゃない?
あと、自分の失敗を話すって、結局は「自分を下げて相手を安心させる」っていう戦略的なものになっちゃうんですよ。つまり、自分を「ちょっとダメな人」として見せることで、親近感を演出するっていう。
でも、それってよく考えたらセルフブランディングですよね。「完璧じゃない自分」っていうキャラを演じてるだけで、本当の自分を見せてるわけじゃない。つまり、安心感を与えるっていうのは、相手を操作してるっていう側面もあるわけで、あざとさが出ちゃうと逆効果なんですよ。
なので、「失敗談で距離を縮める」っていうのも、やり方間違えるとただの自虐ネタおじさんになるんで、気をつけた方がいいんですよね。
タイミングと空気を読むことの限界
雑談の「タイミング」って、そんなに管理できるもんじゃない
「雑談はタイミングが重要」って言われるんですけど、そもそもタイミングを見計らって雑談するって、そんな器用なことみんなできます?って話なんですよ。会議の前に軽く話すとか、打ち合わせの前に場を和ませるとか、言うのは簡単ですけど、実際の現場では緊張してたり、相手が忙しそうだったりして、「今、話しかけたら迷惑かも…」って思っちゃう人がほとんどなんですよ。
結局のところ、雑談って「間」を読まないといけないし、その「空気を読む」能力がないとタイミングなんて見極められないんです。で、それができる人は最初からコミュ力ある人なんですよね。だから、タイミングを意識するっていうより、「自分が話したいと思ったら話す」くらいの自然さがあった方が、よっぽど健全だと思うんですよ。
空気を読む=疲れるコミュニケーションになりがち
空気を読むって、言い換えると「相手に合わせて自己抑制する」ってことなんですよ。それって、結局すごく疲れるんですよね。雑談って本来、気軽な会話のはずなのに、「この話しても大丈夫かな」とか「相手の気分どうだろう」とかを気にしながらやる時点で、もう雑談の体をなしてないんですよ。
もっと言うと、日本人って空気を読みすぎて、沈黙を恐れすぎてるんですよ。沈黙が怖いからこそ、無理に話題を振って、結局うわべだけの話になるっていう。雑談って沈黙も含めて「自然体」が大事で、タイミングとか空気を読みすぎると、ただの気疲れコミュニケーションになっちゃうんですよね。
教養の正体と、その落とし穴
「教養」は広く浅く、が一番いい
この本の中で「教養を身につけよう」っていうのが何度も出てくるんですけど、要は「雑談で使えるような教養」って、広く浅くが正解なんですよ。深く掘り下げた専門知識って、普通の会話では使いにくいし、相手も興味持てなかったりします。
たとえば「第二次世界大戦中のドイツ軍の戦略」について詳しくても、それって普通の人との雑談で使えないじゃないですか。でも、「最近ドイツ行ったんですけど、ベルリンの歴史的な建物がすごくて…」みたいな話だったら、雑談としては成立するんですよ。
つまり、「使える教養」って、情報の引き出しを増やすことじゃなくて、「話を広げるための種をまいておく」っていうことなんですよね。だから、専門知識をひけらかす人ほど、雑談下手になりやすいっていう皮肉な話なんです。
知識がある=話が面白い、ではない
もう一つ誤解しがちなのが、「知識がある人は話が面白い」って思い込むことなんですよ。でも実際には、知識が多いだけの人って、話が一方通行になりがちなんです。相手の反応を見ないで話し続けちゃう。で、相手がついてこれなくなっても気づかない。
それって、結局「雑談」じゃなくて「講義」になっちゃうんですよね。だから、「自分が知ってることをいかに面白く話すか」より、「相手が話したいことにどう乗っかるか」の方が重要なんですよ。
教養っていうのは武器じゃなくて、相手との会話をつなぐための橋みたいなもんで、それを使って相手の話を引き出したり、共通点を見つけたりするのが上手な人が、結果的に雑談もうまくなるんですよ。
雑談の本当の価値って何なのか?
雑談=人間関係の潤滑油、って思いすぎじゃない?
雑談が人間関係を深めるっていうのは、確かに一理あるんですけど、それを過剰に期待しすぎるのもどうかと思うんですよね。雑談ってあくまで「余白」であって、それが本質じゃないんですよ。
ビジネスの場でも、「会議前に雑談をしておくと、その後の議論がスムーズになる」とか言われますけど、それって元々関係が悪くなければの話なんですよ。嫌な上司と無理やり雑談しても、心は開けないし、業務がスムーズになるとも限らない。
だから、雑談を万能薬みたいに扱うのは危険で、「仲良くなるために雑談する」んじゃなくて、「仲良くなった結果として雑談ができるようになる」くらいの方が自然だと思うんですよ。
雑談が得意じゃない人はどうすれば?
で、問題は「雑談が苦手な人が、どうすればいいか」なんですけど、結論から言うと、無理に雑談をがんばらなくてもいいと思うんですよ。人と話すのが苦手な人が、無理に雑談をしても疲れるだけですし、逆に不自然な空気を作ることもあるんで。
それよりは、「雑談しない代わりに、ちゃんと仕事で結果を出す」とか、「雑談よりも丁寧な文章でやり取りする」とか、自分の得意なスタイルで信頼を築いていけばいいと思うんですよね。
雑談って、向き不向きがあるので、「全員が雑談力を身につけなきゃいけない」っていう考え自体が、ちょっと押しつけがましいんですよ。向いてない人は向いてないなりの戦い方をすればいいんです。
まとめ:雑談力の正体とその「効率性」
雑談力=情報処理力+興味関心+人間観察
結局のところ、雑談力って「情報処理力」と「相手への興味関心」、そして「人間観察力」の掛け算なんですよ。で、これって全部一朝一夕で身につくものじゃないし、テクニックでどうにかなる話でもない。
相手の話から情報を素早く読み取って、それに自分の知識や経験をつなげて、さらに相手の反応を観察しながら展開を調整するっていう、かなり高度なスキルなんですよ。だから、「質問の用意をしときましょう」とか「リアクションを取りましょう」とかっていうアドバイスは、基礎の基礎なんですよね。
むしろ、「なんで自分は雑談が得意じゃないのか?」ってところから考えた方が早いです。興味がないのか、情報がないのか、観察ができてないのか。その原因によって、伸ばすべき部分も変わってくるわけで。
雑談力の磨き方=自分のクセを知ること
そして一番大事なのは、「自分の雑談のクセを知ること」なんですよ。話しすぎる人なのか、聞きすぎる人なのか、笑いを取りたがる人なのか、無難に逃げる人なのか。それを知るだけで、かなり雑談の精度は上がります。
教養を増やすよりも、自分のパターンを把握する方が効果的なことって多いんですよね。雑談って、相手を知る前にまず自分を知る作業なんですよ。だから、本を読むだけじゃなくて、日々の会話の中で「自分はどういう話し方してるか?」って意識することが、一番の練習になると思うんですよね。
結局、雑談って「会話の筋トレ」みたいなもんで、正しいフォームを身につけたうえで、回数をこなしていくしかないんです。で、その「フォーム」ってのが、自分を知ることなんです。

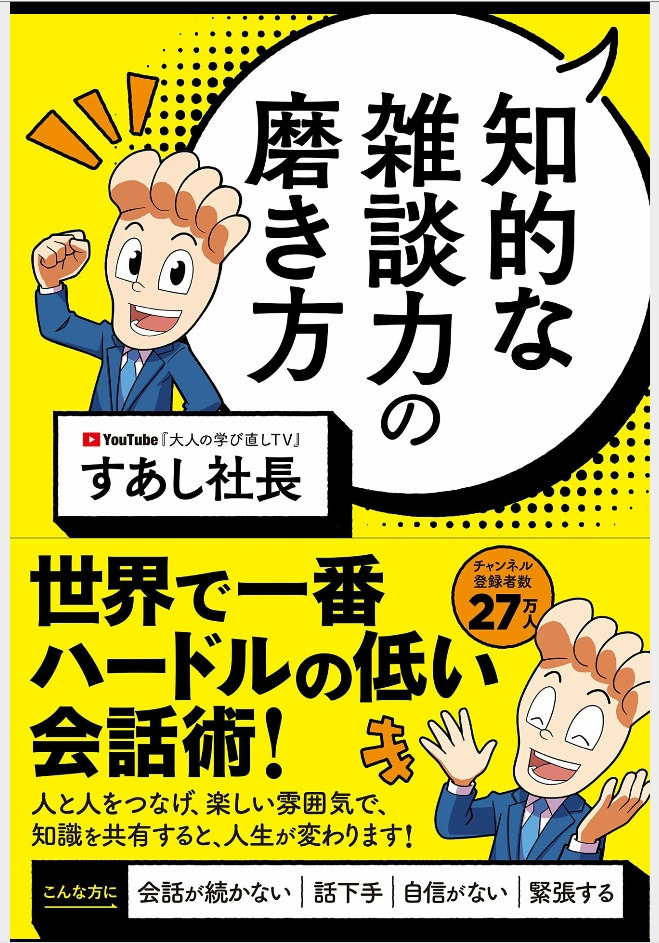

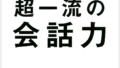
コメント