説明の本質とは「自分を消すこと」
要は、自分の話を聞いてほしいだけの人が多すぎる
この本を読んでまず最初に思うのは、「説明が上手い人」って言い換えると「自分の存在を薄くできる人」なんですよね。要は、相手の理解を最優先にして、自分の伝えたいことは二の次にしてる。だから相手に響くし、理解されやすい。世の中の多くの人がやってるのは「説明」じゃなくて「自己主張」です。で、その違いがわかってないから、話が伝わらない。結局のところ、自己中心的な説明って、誰も聞いてくれないんですよ。
説明で重要なのは、自分の考えや感情をどれだけ抑えられるかってこと。つまり、自己抑制のスキルなんです。そこにPREP法とか「相手ファースト」っていうテクニックが入ってくる。要は、説明のテクニックって「自分を抑えて、相手に合わせる」ことの体系化であって、自分の話したいことをうまく伝える技術ではないんですよね。
PREP法の真価は「時間の短縮」
PREP法(Point→Reason→Example→Point)って、まあビジネス書とかプレゼン本では定番中の定番なんですけど、本質的に優れてるのは「相手の時間を奪わない」ってことなんです。多くの人って、ダラダラ前置きを話して、最終的に「で、結局なに?」って聞かれる。それって、相手の時間を無駄にしてるわけで、社会的なコストとしてめちゃくちゃ非効率なんですよ。
要は、PREP法って「相手の脳内プロセスのショートカット」なんです。結論を先に言うことで、相手は自分の聞く体勢を整えられるし、理由と具体例で納得の階段を登らせる。そして最後にもう一度結論を言うことで、記憶に定着させる。これって、話す側の論理力というより、聞く側の処理能力を意識した配慮なんですよね。だから、PREP法が使える人って、頭がいいというより「他人の脳の使い方を理解してる人」なんです。
相手の脳をハックする技術
右脳へのアプローチは「説明の裏口入学」
この本では、「相手の右脳を刺激する説明」ってのが紹介されてて、たとえ話やイメージを使えって書かれてます。で、これって要は「感情に訴えろ」ってことなんですけど、もっと言うと「論理で理解できない人に、別ルートで理解させる方法」なんですよ。論理で納得できる人って、たぶん全体の2〜3割くらいで、残りは感覚や雰囲気で判断してる。そういう人にいくらロジカルに説明しても伝わらないんです。
で、右脳って言い方してるけど、実際には「たとえ話でストーリーを作る」ってことなんですよね。例えば「このサービスは、まるでNetflixで映画を見るような感覚です」って言われたら、それがどんなに複雑なプロダクトでも直感的にイメージできる。つまり、論理的に説明するより、感情に寄り添って、視覚的にイメージを浮かばせる方が早いってことです。だから、「説明が上手い人」は、論理を積み上げるより、相手の感覚に寄り添う道を選んでる。
説明とは「翻訳作業」だと思った方がいい
で、もう一個面白いのが、「相手のレベルに応じた言葉選び」ってやつ。これって要は「専門用語を使うな」って話なんだけど、もっと本質的には「自分の中の世界を、相手がわかる言語に翻訳する能力」なんですよ。で、ここができない人が多い。
例えば、エンジニアが「このシステムはマイクロサービスで設計されてて〜」とか言っても、営業の人には何のこっちゃわからないわけですよ。でも、「部品ごとに分けたおもちゃみたいな設計なんです」って言えば、あっさり伝わる。だから、説明って「自分の知ってる世界を、いかに相手の知ってる世界に変換できるか」っていう翻訳スキルなんです。
で、それをやるには、相手がどんな知識レベルで、どういう価値観で、何に興味があるかを先に想像する力が必要になる。だから、説明が上手い人って、言葉がうまいんじゃなくて、想像力がある人なんですよね。
「説明」と「説得」はまったく違う
理解されることと、納得されることの違い
この本はあくまで「説明の技術」を扱ってるけど、結構多くの人が「説明=説得」って思ってる。でも、実はこの2つはまったく違う。説明ってのは、相手に「理解させる」ことであって、納得させる必要はないんですよ。逆に説得ってのは、「理解+納得」の両方が必要になる。
で、説得を前提に説明しようとすると、相手の反発が生まれる。なんでかっていうと、「お前の意見を押し付けてきてる」と感じるから。だから、「説得するための説明」は、むしろ逆効果になることが多い。説明がうまい人って、相手に押し付けるんじゃなくて、「わかりやすく伝える」ことに徹してる。つまり、理解されることに特化してて、その結果、相手が自分で納得するって流れを作ってる。
感情に訴えるか、データで示すかの二択ではない
本書で「感情に訴えろ」と「具体的な数値を示せ」が同時に出てきてて、これって一見矛盾してるように思えるんですけど、実は両方必要なんですよ。要は「右脳にも左脳にもアプローチしろ」ってことなんですね。で、どっちか一方に寄りすぎるとバランスが崩れる。
数字だけの説明って、冷たいし面白くない。でも感情だけの説明って、説得力が弱い。だから、数字で裏付けつつ、感情にも寄り添う。例えば「売上が前年比で30%アップしました」ってだけじゃなくて、「これによって、現場の社員が笑顔になった」みたいな補足があると、聞いてる側の納得度が変わる。
この両輪をうまく回すのが「説明力」の真骨頂であって、どちらか片方に偏った瞬間に、相手の理解と共感は離れていくんです。
説明力とは「相手を動かす力」
「説明して終わり」は、ただの自己満足
前半では「説明=理解させること」と述べましたが、実はそれだけでは不十分だったりします。なぜなら、説明の目的って「理解させること」で終わりじゃなくて、「行動を起こさせること」なんですよね。要は、説明がうまい人って、「相手の頭」と「相手の体」の両方を動かせる人なんです。
「この資料を見て理解しました。でも行動は変わりません」って状況って、実は日常的に多いんですよ。で、これは説明が悪いんじゃなくて、目的設定がズレてる。行動を促したいなら、「感情」「納得」「納得後のモチベーション」の3つを組み合わせないとダメなんです。だから、説明って一方的な情報伝達じゃなくて、「相手が動く前提で逆算して構築するもの」なんですよね。
フィードバックを取るのは「説明の結果確認」ではない
この本では「説明の後にフィードバックをもらえ」と推奨してますけど、それって要は「自分が正確に伝えられたかの確認作業」なんです。でも、ほとんどの人が「自分の言いたいことは全部言えた」って自己満足で終わってる。で、相手が理解してるかどうかを確認しない。だからズレる。
説明って一種のインタラクションなので、双方向のやりとりなんですよ。自分が話した内容に対して、相手がどう感じたのか、どこでつまずいたのか、何が響いたのかを把握しないと次に繋がらない。つまり、フィードバックは「説明の結果報告」じゃなくて、「次の説明の設計素材」なんですよね。
そして、この考え方が根付いてる人ほど、説明の精度が上がっていく。逆に、フィードバックを「おまけ」と思ってる人ほど、ずっと同じ説明ミスを繰り返す。結局、改善サイクルを回せるかどうかが、説明力を伸ばす分水嶺なんです。
情報の「加工力」が説明を決める
情報を整理できない人は、何を言っても伝わらない
どんなにいい情報を持っていても、それを整理して提示できなければ意味がないんですよ。情報って「そのまま渡すと毒」なんですよね。例えば「今日の天気は、北西からの低気圧の影響で湿度が高まり〜」とか気象庁的に正確な情報を渡されても、聞く側からすると「結局傘いるの?」ってなるわけです。
で、説明がうまい人って、こういう複雑な情報を「傘が必要かどうか」っていう相手の判断軸に合わせて出力する。つまり、情報を「使える形に加工する」能力がある。それが論理力とか文章力の正体だったりするんですよ。
だから、「情報をまとめる力」ってのは、単なるスキルじゃなくて「相手の判断をサポートするための前処理能力」なんです。要は、料理でいう「下ごしらえ」が説明には必要で、それを怠って生の情報を出す人は、相手の胃袋を壊すんです。
仮説思考が説明に与える「時短効果」
仮説思考って、聞いたことある人多いと思うんですけど、これが説明にめちゃくちゃ効くんですよ。なんでかっていうと、説明って本来、相手の知識レベルや関心に応じてチューニングしなきゃいけないんですよ。でも、相手に聞いてから合わせてたら遅い。だから仮説を立てて、「たぶんこの人はこういう前提で聞いてるはず」と想定して話す。
で、もしズレてたら、そこから微調整すればいい。仮説が当たってれば、相手は最初からスムーズに理解してくれるし、外れててもズレを確認して再構成できる。つまり、説明のスピードと精度の両方を高める方法なんですよね。これをやらないで「最初から全部説明しよう」とする人は、結果的に相手の時間を奪ってるんです。
仮説思考って、決して頭のいい人だけが使える技術じゃなくて、むしろ「相手を思いやるための予測能力」なんですよ。だから、仮説を立てて話す人は、論理的に見えて、実はめちゃくちゃ優しい。
説明は「技術」ではなく「哲学」
「相手を尊重する姿勢」が技術を活かす
PREP法とか、右脳刺激とか、たとえ話とか、いろんなテクニックは紹介されてるけど、結局どれも「相手へのリスペクト」がないと成立しないんですよ。だって、説明って「自分の言葉を相手の中に置かせてもらう作業」なんですよ。それって、めちゃくちゃ繊細で、一歩間違えたら「押し付け」になる。
「この人は自分を理解しようとしてる」って相手が感じてくれた時に初めて、説明は成功する。だから、説明がうまい人って、言葉より先に「姿勢」がうまい。相手の立場に立って、相手がどう受け取るかを常に意識してる。で、その結果、言葉の選び方や構成の仕方が自然と最適化されていく。
つまり、説明がうまい人って、技術を積み重ねたんじゃなくて、「人間理解を深めた結果、説明もうまくなった」ってパターンが多い。だから、説明力って「話す力」じゃなくて「相手を見る力」なんですよ。
説明上手は、実は「傾聴上手」
そして最後に強調したいのが、説明がうまい人って、実は「聞く力」が異常に高いってこと。話し上手は聞き上手ってよく言うけど、説明に関しても完全にそれが当てはまる。相手がどういう言葉で話してるか、どういう順番で理解してるか、どこで止まってるか、そういう細かい反応を観察してる。
つまり、説明って一方通行に見えて、実は「リアルタイムの双方向コミュニケーション」なんです。で、それができる人は、言葉だけじゃなくて、相手の空気や感情の流れまで読んで調整してる。これはテクニックだけじゃ身につかない部分で、人間的なセンスや経験が問われるところ。
結局、説明力を伸ばしたいなら、「話す練習」よりも「聞く練習」をした方が効果が高いんですよね。で、そこに気づけるかどうかが、説明のプロと素人の違いなんです。

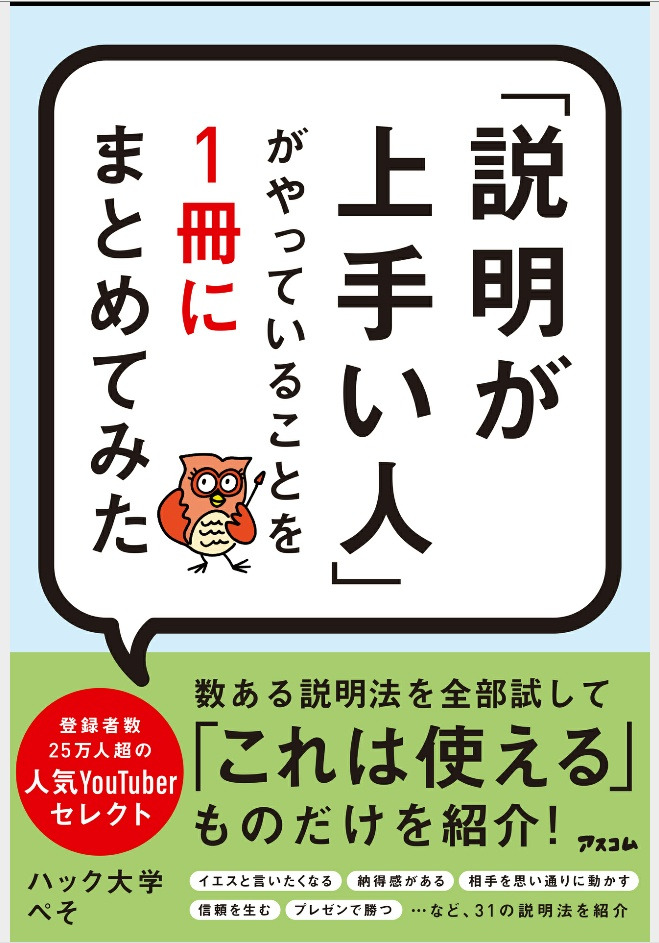


コメント