医療デマの拡散と「信じる人の心理」
要は、信じたいものしか見ない人が多いんですよね
ネット上で「がんは放置すれば治る」とか「ワクチンは毒だ」とか、そういう医療デマが広まってるんですけど、要はこれって「信じたいものを信じる」っていう人間の性質の問題なんですよね。だから、どれだけ正しい情報を提供しても、「でもYouTubeでこの人が言ってた」とか、「SNSでシェアされてるから真実だ」みたいなロジックが平気で通用しちゃう。
それって本質的には、合理的に物事を判断できない人が、感情ベースで情報を選んでるからなんですよ。で、そういう人たちは医療知識がないから、ちょっと難しい単語が並んでると「なんかすごい」って思っちゃう。つまり、情報格差がそのまま信じ込みやすさに直結してるって話なんです。
「不安ビジネス」が医療デマを支えてる
医療デマが広がる背景には、「不安を煽ると金になる」っていうすごくシンプルな経済合理性があるんですよ。要は、病気に不安を感じてる人って、お金を出すんですよね。藁にもすがる思いってやつです。
例えば「飲むだけで痩せるサプリメント」って、冷静に考えたらそんなものあるわけないんですけど、でも「痩せたい」っていう願望に漬け込めば売れる。だから企業も「売れるなら出す」っていうだけで、そこに善悪の判断なんてないんですよ。これって別に医療に限らず、詐欺的なビジネス全般に言えることなんですけど。
結局、企業ってのは儲けるのが仕事だから、倫理的なことは後回しになるんです。で、法律にギリギリ違反しない範囲で「誇大広告」をやる。だから、行政がようやく動いても、すでに相当数の人が騙されてるっていう。
メディアの責任とその構造的欠陥
そもそも検索上位に出る仕組みがおかしい
WELQ問題みたいに、検索結果の上位にウソ情報が出てくるっていうのは、本来おかしいんですよ。でも、GoogleもYahooもビジネスだから、結局は「クリックされやすい」情報を上に出すっていうアルゴリズムにしてるんですよね。で、そうすると、科学的根拠よりもセンセーショナルなタイトルが勝つ。
つまり、科学って基本的に「慎重」な表現を使うんですよ。「可能性がある」とか「まだ研究段階」とか。でも、ウソ情報って「絶対に効く!」「がんが消える!」みたいに断定できる。だからネット上では後者の方が目立つし、拡散されやすいんですよね。これって情報の構造的な欠陥ですよね。
BuzzFeedの動きは評価されるべきですけど…
WELQに対してBuzzFeedが取材して閉鎖に追い込んだのは、それはそれで価値ある動きだと思いますよ。でも、要はそれって「例外」なんですよね。本来であれば、メディア全体に自浄作用があって当然なわけですけど、ほとんどのメディアって「アクセス数が命」なので、センセーショナルな情報を扱う方向に流れるんですよ。
つまり、構造的に「真実よりもバズる情報」が優先されるシステムなんです。で、それに広告主も乗っかってくる。なので、「真実を伝える」っていうジャーナリズムの原点は、すでに崩壊してるんじゃないかって思うんですよね。
不確実性の世界でどう生きるか
医療って、そもそも100%じゃないんですよ
これ、意外と多くの人が理解してないんですけど、医療って基本的に「確率論」なんですよね。どんなに優れた治療でも、「必ず治る」なんてことはない。だから、ちょっとでも効果があるとされる「代替療法」にすがっちゃう人が出てくるんですけど、それって完全に「心理の穴」を突かれてるわけです。
免疫療法とかもそうですけど、「何もしないよりマシ」とか「希望を持てる」みたいな感情が先に立つんですよ。でも、それで数百万とか取られたら、もはや詐欺と変わらない。で、それに騙されても、「試しただけで後悔してない」とか言っちゃう。いや、それ後悔しろよって話なんですよ。
医療者との会話って、そんなに難しいことじゃない
あと、医療デマに騙されないためには「主治医とちゃんと話すことが大事」とか言われるんですけど、要はそれって「わからないことを素直に聞けるかどうか」だけなんですよね。でも、なんか「先生に聞いたら失礼なんじゃないか」とか、「変なこと言ったら恥ずかしい」とか、そういう変な遠慮がある。
別に医者も人間なんだから、「何がどう効くのか」「リスクは何か」って聞けば、ちゃんと答えてくれますよ。むしろ聞かない方が医者にとって困るんですよ。だから、ちゃんと対話しようとしない人が「ネットで調べました」って出してくる怪しい情報に引っかかる。で、それを医者に見せて「これどうなんですか?」ってドヤ顔する。いや、それ調べ方が間違ってるから。
情報リテラシーとその現実的限界
5W2Hとか言っても、使いこなせる人ほとんどいないんですよ
「情報を正しく判断するには5W2Hを使え」って話があるんですけど、それって要は「ちゃんと考えろ」って言ってるだけなんですよね。でも、実際に5W2Hを意識してネット情報を見てる人なんて、ほぼいないと思うんですよ。なぜなら、めんどくさいから。
「Whoが発信してるか」とか、「Whenの情報か」とか、考えようと思ったら時間もかかるし、それなりの知識もいる。でも、人間って基本的に「楽したい」んですよ。だから、タイトルだけ見て、「あ、これ効きそう」って飛びつく。つまり、「5W2Hが大事」って言ってる時点で、その情報を扱える層が限られてるってことなんですよ。
で、その結果、知識のない人たちほど、医療デマに騙される。これってもう、情報格差じゃなくて、「思考格差」って言った方がいいんじゃないですかね。
リテラシー教育の難しさは、効率の悪さなんです
じゃあ、「みんなにリテラシー教育をしましょう」って言うと、それもまた問題なんですよね。というのも、リテラシーって一朝一夕で身につかないし、しかも個人差が大きい。教えるのにコストがかかるし、理解できない人には一生理解できない。
で、そんな中途半端な教育より、「間違った情報を上位表示させない」みたいなプラットフォーム側の対応の方が、はるかに効果的なんですよ。でも、結局のところ、GoogleもYouTubeも、そこに対して本気出してない。だから、「騙される人がバカ」って切り捨てるよりも、「騙されにくい仕組み」をどう作るかの方が重要なんじゃないですかね。
ビジネスとしての医療と、倫理の境界
「経済合理性」は悪ではないけど、限度がある
よくあるのが、「企業も商売だからしょうがない」って意見なんですけど、それって結局、消費者が損をする構造を黙認してるって話なんですよね。サプリメントなんかもそうで、「痩せる」「健康になる」っていう漠然とした願望に対して、「根拠があるかどうか」なんて気にしない人が大半。
でも、それって詐欺の温床になるわけで、ある程度は規制しないとまずいんですよ。だから行政が入ってくる。でも、その時点で「売れた後」なんですよね。つまり、「もう被害者が出た後にしか動けない」っていうのが現状の限界なんですよ。
企業が悪いというより、その「ルールを整えるのが遅い社会」の方が問題なんじゃないですかね。
標準治療を疑う人の論理破綻
あと、「標準治療を受けないで独自療法に頼る人」って、ちょっと前なら陰謀論者扱いされてたんですけど、今や割と普通にいるんですよ。で、彼らの言い分が「病院は儲けたいから本当の治療を教えてくれない」っていう、映画みたいな陰謀論なんですけど、それって論理的に破綻してるんですよね。
要は、「儲けたいなら、効く治療を出すに決まってる」んですよ。だって治った方が満足度も高いし、再診率も上がるから。なのに、あえて「効かない治療を推してる」って考える方が、よっぽど非合理的なんですよ。
結局、そういう人たちって「医療に対する不信感」だけで動いてて、事実ベースじゃないんですよね。
個人ができる現実的な対策とは
「自分で判断する」ってのは無理ゲーです
「複数の情報源から確認しましょう」とか、「厚生労働省のページを見ましょう」とか言うんですけど、そんなこと一般人に期待する方が無理があると思うんですよ。要は、みんな忙しいし、専門用語はわからないし、英語の文献なんてもっと読めない。
だから現実的には、「ちゃんとした人を信じる」っていうスタンスの方が効率いいんですよね。で、その「ちゃんとした人」が誰かを見極める力が必要なんですよ。でも、SNSが発達した今、肩書きだけで人を信じると騙されることもある。なので、「誰を信用するか」の選球眼こそが、今の時代の最大の武器なんですよ。
感情ベースの選択を減らすには「余裕」が必要
人間って、感情的になってる時ほど、騙されやすいんですよ。病気になって不安になってる時、家族が倒れて焦ってる時、そういう時に「奇跡の治療法」みたいなのが目に入ると、理性より先に感情が動く。
だから、「感情を落ち着かせる時間」ってすごく大事なんです。要は、即断即決しない。何か健康や病気に関わる情報が目に入った時に、「ちょっと一晩寝かせる」ってだけで、かなり冷静な判断ができるようになるんですよ。
つまり、医療デマに引っかからないための最大の対策って、「余裕を持つこと」なんですよね。



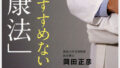
コメント