うーん、この『パーパス・マネジメント』の内容なんですけど、要するに「社員の幸福と企業の成功は直結するよね」って話ですよね。で、そのためにCHO(Chief Happiness Officer)を設置したり、パーパスの共有をしたり、感謝カードとか幸福度アンケートをやると良いですよ、という提案が書かれてると。まあ、悪くはないんですけど、「それって本当に必要ですか?」って話なんですよね。
パーパスって、本当に全員が必要なの?
全員が「意義ある仕事」を求めるわけじゃない
この本では「パーパス=存在意義」が仕事の満足度と幸福につながる、って前提になってますけど、そもそも「そんなこと考えてない人」も多いんですよね。仕事はお金のためと割り切ってる人もいるし、やりがいよりも「楽で給料がいい仕事」のほうがいいって考える人もいる。そういう人たちに「君のパーパスは?」って聞いても「いや、別に……」ってなるだけですよね。全員がパーパスを持つべき、みたいな前提自体がちょっと無理があるんじゃないかと。
「幸せになれば生産性が上がる」の本当のところ
あと、「幸福度が高いほうが生産性が上がる」っていう考え方、まあ研究結果とかもあるっぽいんですけど、「それって本当に因果関係があるの?」って話なんですよね。幸せだから仕事がうまくいくのか、仕事がうまくいってるから幸せなのか、どっちが先かよくわからない。で、現実を見ると「ブラック企業のほうが売上は上がってる」みたいな例もあるわけで。理想論としてはいいんですけど、「じゃあ、この本の内容を全部の企業がやったら本当に儲かるの?」って言われると、ちょっと疑問ですよね。
CHOって本当に必要?
人事部と何が違うのか問題
「CHO(Chief Happiness Officer)」って要するに「社員の幸福度を上げる人」ってことですよね。でも、それって「人事部の仕事と何が違うの?」って話になるんですよ。人事部も社員のモチベーションや定着率を考えて施策を打つわけで、CHOという役職を新しく作る必要があるのかどうか、正直疑問ですね。CHOの仕事って、「人事の人が少し意識を変えればできること」ばかりなんですよね。
企業の目的は「社員の幸福」じゃない
あと、CHOの考え方って「社員が幸せになれば会社もうまくいく」っていう理想論に寄りすぎてて、実際のビジネスの現場とちょっとズレてるんじゃないかと思うんですよね。企業の目的って、「利益を出すこと」じゃないですか。もちろん、社員が幸せであるほうが望ましいですけど、それが目的になった瞬間に「じゃあ、給料を上げ続ければいいんですか?」って話になって破綻するんですよ。幸福度って無限に上げられるものじゃないし、そもそも全員が同じことで幸せになるわけでもないんですよね。
「働き方改革」の本当の課題
残業を減らしても幸せにならない理由
この本では「働き方改革の本質は社員の幸福」って書いてありますけど、これもちょっと現実とズレてるんですよね。例えば「残業を減らせば社員は幸せになる」っていう考え方があるんですけど、実際には「給料が減ると困る」って人もいるわけで。だから「残業削減=幸福度アップ」じゃないんですよ。むしろ「給料が下がったから副業しなきゃいけない」とか、逆にストレスが増えることもあるんですよね。
結局「自由度」が大事
じゃあ、どうすればいいのかって話なんですけど、結局「選択肢の自由」があるほうがいいんですよ。残業したい人はすればいいし、したくない人はしなくていい。テレワークしたい人はすればいいし、会社に来たい人は来ればいい。それぞれの人が「自分に合った働き方」を選べるようにするのが、一番の働き方改革なんじゃないかと。こういう「柔軟性」のほうが、幸福度を上げるには重要なんじゃないですかね。
「幸福度を測ること」の無意味さ
幸福度って主観的すぎる
幸福度を測るって話も出てきますけど、そもそも幸福って主観的すぎて、数値化してもあんまり意味ないんですよね。「今日は5点です」とか言われても、「それって昨日と比べてどうなの?」ってなるし、長期的なデータを取ったところで「だから何?」って話になるんですよ。で、これを改善するために施策を打っても、「幸福度が本当に上がったのか?」を測る方法がないんですよね。
「幸福の押し付け」になりがち
あと、企業が「社員の幸福度を上げる」っていう発想自体が、「なんか気持ち悪いな」って思うんですよね。会社は福利厚生とか労働環境を整えるのが仕事で、「あなたを幸せにします!」みたいなことを言い出すのは、ちょっと余計なお世話なんじゃないかと。むしろ「幸福度アンケートを毎週やります」とか、「感謝カードを配りましょう」とか言われると、「いや、そういうのいいんで普通に仕事させてください」ってなる人もいると思うんですよね。
「感謝カード」とかいう謎文化
感謝を強制するのは逆効果
この本では「感謝カード」なるものを導入して、社員同士で感謝を伝え合う仕組みを作るのがいい、って話が出てくるんですけど、これって「やらされ感」が出た瞬間に逆効果なんですよね。「感謝しましょう!」って強制されると、人間って逆にやりたくなくなるんですよ。感謝って本来、自然に生まれるものじゃないですか。感謝カードを書かなきゃいけないとなると、「あー、今週まだ感謝してないから、適当に誰かに書くか」みたいになって、完全に形骸化するわけです。で、「みんな感謝し合ってます!」みたいな空気を作っても、それが本音じゃなかったら意味ないんですよね。
職場に「仲良しごっこ」はいらない
あと、こういう「感謝を表現しましょう」みたいなのって、職場を「仲良しクラブ」にしちゃうんですよね。もちろん、職場の雰囲気が良いのは大事ですけど、全員が「いい人」になる必要はないし、むしろ「いい人しか評価されない」って空気になると、かえって息苦しくなるんですよ。ビジネスの場では、多少の衝突や議論は必要だし、「仕事ができる人」が評価されるべきで、「感謝カードを書いた回数が多い人」が評価されるのって、ちょっとズレてるんじゃないかと思うんですよね。
「パーパス共有ミーティング」の虚しさ
定期的にやると飽きる
「パーパス共有ミーティングを毎月やりましょう!」みたいな話も出てくるんですけど、これって続けていくと、だんだん形骸化するんですよね。最初のうちは「なるほど、こういう意義があるのか」と思うかもしれないですけど、毎月やるとなると「またこれか……」ってなるのがオチです。で、参加者は「とりあえず適当に意見を言っとけばいいか」とか、「上司が満足するようなコメントを言えばいいか」みたいな感じになって、結局、時間の無駄になるんですよね。
個人の価値観と会社の価値観はズレるのが当たり前
この本の根底にある考え方として、「会社のパーパスと個人のパーパスを一致させよう!」っていうのがあるんですけど、そもそも「全員が同じ価値観を持つ」なんてありえないんですよね。例えば、会社が「世界を変える!」って言ってても、社員の中には「いや、俺は給料のために働いてるだけなんで」って人もいるわけで。そういう人たちに「君のパーパスは?」って聞いても、「いや、特にないです」ってなるんですよ。で、「じゃあ、考えましょう!」ってなると、それってもう強制なんですよね。価値観の押し付けをしている時点で、それって「自由な組織」じゃなくて「思想統制」みたいになってるんじゃないですかね。
ティール組織の現実問題
「自由に働く」は理想論
この本では「ティール組織」っていう概念が出てきて、要するに「社員が自発的に動くことで、組織が成長する!」みたいな話なんですけど、これって現実的に考えると、うまくいかないケースが多いんですよね。なぜかというと、「自発的に動ける人」と「指示がないと動けない人」っていうのは、必ずいるからです。で、ティール組織みたいに「みんなが自律的に動くべきだ!」ってなると、後者の人たちは完全に迷子になるんですよね。「何をやればいいのか分からないけど、勝手にやれって言われてる」みたいな状況になって、結果的にパフォーマンスが落ちるんですよ。
「リーダーがいなくても成り立つ」なんて幻想
ティール組織って「ヒエラルキーがなくても組織は回る!」っていう理想があるんですけど、結局、人間って「指示する人」と「指示される人」に分かれるんですよね。どれだけフラットな組織にしても、「暗黙のリーダー」みたいなのが生まれて、その人が結局仕切ることになるんですよ。で、そういう非公式なリーダーができると、正式な役職もないのに「実質的な上司みたいな人が生まれる」みたいなことになって、かえって混乱するんですよね。結局、人間の集団って「指揮系統が明確なほうが動きやすい」っていうのは、歴史的に証明されてるんじゃないかと思います。
結局、「幸福」は個人に任せるのが一番
会社ができるのは「環境を整えること」だけ
この本では「企業が社員の幸福を最大化するべき!」みたいなことが書かれてるんですけど、これって結局、「企業がそこまでやる必要ある?」って話なんですよね。会社がやるべきなのは、「社員が働きやすい環境を作ること」までであって、「社員の幸福度を上げること」じゃないと思うんですよ。例えば、「給料をちゃんと払う」「労働時間を管理する」「パワハラを防ぐ」とか、そういう最低限のことをしっかりやるだけで、十分なんですよね。で、あとは個人が「何をすれば幸せなのか」を自分で考えるべきなんじゃないですかね。
「幸福経営」の限界
最後に、この本のテーマである「幸福経営」についてなんですけど、これって結局、「人による」としか言えないんですよね。ある人にとっては「自由に働ける環境」が幸せでも、別の人にとっては「安定した給料と明確な指示」が幸せかもしれない。そういうバラバラな価値観を持つ人たちを「一つの幸福論」でまとめようとすると、無理があるんですよ。だから、会社ができるのは「選択肢を用意すること」までで、「全員を幸せにする!」みたいなスローガンは、現実的にはあまり意味がないと思うんですよね。

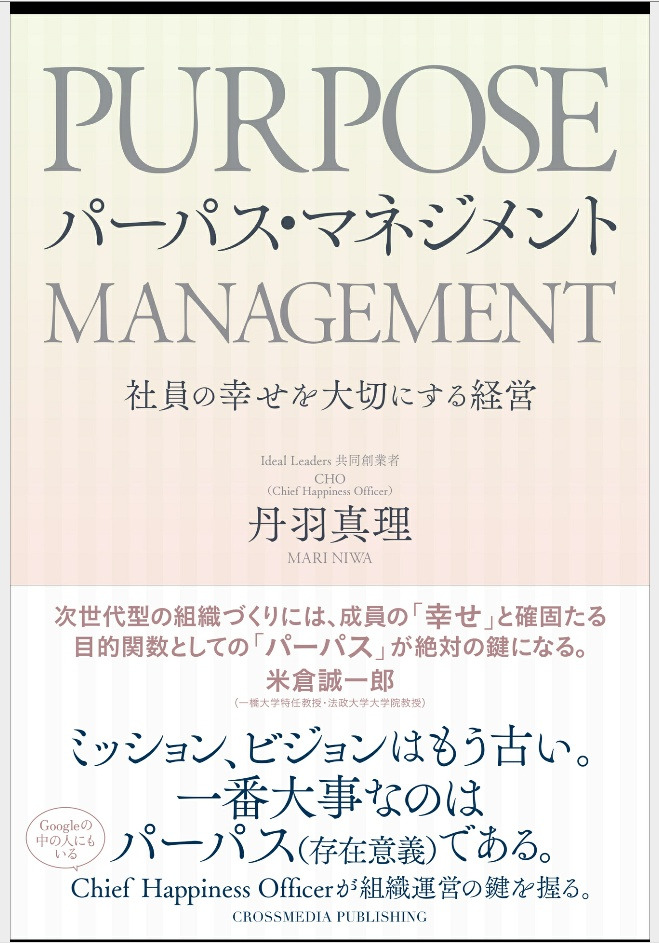


コメント