「超コミュ力」の本質を見抜く視点
「話す力より聞く力」の嘘と真実
まず、「コミュニケーションに話す力はいらない」っていう主張ですけど、それって本当ですか?って話なんですよね。たしかに、聞く姿勢が大事だとか、うなずきが有効だとか、そういう話はよくあるんですけど、結局のところ「聞く」って行為も、ある意味「話す」行為と表裏一体なんですよ。
つまり、相手の話を聞いて適切なリアクションをするには、まず相手の話の文脈を読み取って、それに対して意味のある反応を返す必要があるわけで。その時点で、ある程度「伝える力」つまり話す力がなきゃ成立しないんですよ。だから、「話す力がいらない」って言い切っちゃうのは、ちょっと極端すぎて、論理的に成立しないんですよね。
それに、「聞く力が大事」って言葉が独り歩きして、「何も言わずに聞いていればいい」っていう思考停止に陥る人が増えるのも問題で。聞くって行為にもテクニックが必要で、それはもう一種のアウトプットなんですよ。だから「話す力=コミュ力」じゃないにしても、ある程度の話術や表現力っていうのは、やっぱり必要なんですよね。
「相手に気持ちよく話させる」ことの功罪
で、「自分が話すよりも、相手に気持ちよく話させましょう」っていう提案なんですけど、うん、それって確かに人間関係を円滑にするには有効なテクニックではあるんですよ。ただ、それを「コミュニケーションの核心」って言い切っちゃうと、またちょっと違和感あるんですよね。
だって、それって「相手の話に合わせて自分を押し殺す」っていう行為でもあるわけで。気持ちよく話させるっていうのは、つまり相手の快を優先するってことで、自分の意思や意見を二の次にしてるとも言えるんですよ。
本当に対等なコミュニケーションを求めるなら、「聞くだけの人」っていうのは、むしろ相手から舐められる可能性もあるわけで。要は、「聞くこと」も「話すこと」も、バランスが大事ってことですね。片方に極端に寄っちゃうと、それはもう対話じゃなくて「奉仕」になっちゃうので。
それに、人間って基本的に自己主張したい生き物なので、「聞く専門」ってキャラを貫くのって、かなりストレスたまると思うんですよね。ずっと相手に気持ちよく話させて、自分は我慢って、長期的に見たら続かないんですよ。
コミュ力を「見せかけ」でごまかす技術
「うなずき」と「笑顔」の演出問題
次に、「うなずき」や「笑顔」の効果っていう話ですけど、うーん、それって「営業トーク」みたいなもんで、要はテクニック論なんですよね。相手に安心感を与えるとか、共感を示すっていうのは、確かに会話をスムーズにする手段ではあるけど、それが「本心」じゃない場合もあるわけで。
つまり、表情やリアクションを「演技」でやってるだけだとしたら、それは本当に良いコミュニケーションなんですか?って疑問が出てくるんですよ。相手に安心感を与えるために「笑顔を作る」っていうのは、逆に言えば「自分を偽っている」行為でもあるんですよね。
たとえば、嫌いな上司に対しても「笑顔でうなずく」っていうのが正解だとしたら、それって「コミュ力」っていうより「処世術」なんじゃないですか?って話で。コミュニケーションを「好感度を得るゲーム」みたいに扱ってるのって、ちょっと不健全なんですよ。
だから、うなずきとか笑顔っていうのは、あくまで「表現手段の一つ」であって、「それをやってるからコミュ力高い」とは言えないんですよね。結局、本音と建前のギャップをどう扱うかっていう問題になってくるので。
「SNSフレーズ」の軽薄さ
「すごい」「なるほど」「そうなんだ」っていう3語が、相手の心を開かせる魔法の言葉って紹介されてるんですけど、うーん、それって便利だけど浅いんですよね。だって、その3語って、結局「内容を理解してるかどうかは別として、とりあえず相手に同調してるっぽく見せるための言葉」なんですよ。
つまり、「すごい」って言われても、何がどうすごいのか具体的な言及がなければ、単なる相槌でしかないし、「なるほど」って言っても、それが本当に納得してるのか、それとも「早く話終われ」って思ってるだけなのか分からないわけですよ。
会話を成立させるっていう意味では使えるんだけど、それを多用しすぎると「薄っぺらい人」って思われるリスクもあるんですよね。特に、相手が賢い人だと、「こいつ話合わせてるだけだな」ってすぐバレるんで。
要は、コミュニケーションにおける「共感」って、言葉だけじゃなくて、その背後にある「理解」と「誠実さ」が伴ってないと、意味がないんですよ。ただ「すごい」「なるほど」って言ってるだけの人って、AIチャットボットと変わらないんですよね。
「テクニック重視」の落とし穴
「トレーニングで自然な笑顔」は不自然じゃない?
「鏡の前で笑顔の練習をしましょう」ってアドバイス、うーん、それって本末転倒じゃないですか?自然な笑顔って、「自然に出るから自然」なんであって、「練習して出す」時点で不自然なんですよね。
そもそも、なぜ笑顔が出ないのかってところに向き合わずに、「笑顔を作れ」っていう表面的な対策をするのは、問題の根本解決になってないんですよ。人間関係にストレス感じてるから笑顔が出ないのか、自分に自信がないから表情が硬いのか、その原因を探るほうが大事であって。
笑顔が出ない人に「毎日30秒笑え」って指導するのって、筋トレと同じノリだけど、心の問題は筋肉みたいに単純じゃないんですよ。むしろ、そうやって無理に笑顔を作ること自体が、精神的な負担になって逆効果になることもあるんですよね。
だから、「自然な笑顔はトレーニングで作れる」っていうのは、ちょっと雑なアドバイスで、もっと心理的なアプローチが必要だと思うんですよ。
「否定せず肯定する」ことの限界
「相手の意見を否定せず、まず肯定から入る」っていうのも、なんか理想論すぎるんですよね。実際の会話では、「それは違うでしょ」って言わなきゃいけない場面もあるし、相手が間違ってる場合に肯定から入るのって、逆に不誠実なんじゃないですか?
もちろん、いきなり否定から入ると印象悪くなるのは分かるんですけど、だからといって全部の話を「いいね」で受け止めるのは、ただのイエスマンなんですよ。人間関係において、信頼っていうのは「正直なフィードバック」によって築かれるもので、「なんでも肯定する人」っていうのは、逆に信用されなくなるんですよ。
それに、否定することで生まれる建設的な議論もあるわけで、「否定=悪」っていう発想自体がナンセンスなんですよ。要は、どう否定するかの技術のほうが大事で、「否定を避ける」っていうアドバイスは、ちょっと安易すぎると思いますね。
テクニックの積み重ねと「誠実さ」のジレンマ
「テンポを合わせる」って誰に合わせるの?
「会話のテンポを相手に合わせましょう」っていうアドバイス、確かに理にはかなってるんですよ。ただ、ここで疑問なのが、テンポを合わせるって、結局「誰のリズムが正しいのか」って話になるんですよね。
相手に合わせるってことは、自分のペースを崩すわけで、それが毎回うまくいくとは限らないんですよ。たとえば、早口で話す人に無理して合わせたら、こっちは疲れるし、逆にゆっくり話す人に合わせてたら、「なんかやる気ないな」って思われることもあるんですよね。
で、相手のテンポに合わせることが常に正解かって言うと、必ずしもそうじゃなくて、自分のペースを維持することで信頼されるケースもあるんですよ。結局、どっちが優先されるかって、「その場の目的」によるんですよね。
つまり、「会話を気持ちよく進めたい」のか、「本音をぶつけて議論したい」のか、「ビジネスとして効率を重視したい」のかで、テンポの最適解が変わる。だから、「テンポを合わせろ」ってアドバイスは、状況に依存しすぎていて、普遍的な解じゃないんですよ。
「相手の興味を探る」ことの空虚さ
「初対面で相手の興味を探りましょう」っていう話、たしかに雑談の入り口としては有効なんですよ。ただ、それがコミュニケーションの核心かっていうと、そうでもないと思うんですよね。
なぜなら、「相手の興味」っていうのは、表面的な情報でしかないことが多いから。たとえば「最近ハマってることは?」って聞いて「キャンプですね」と返ってきたとして、それって本当にその人を知ったことになるんですか?って話なんですよ。
つまり、「興味があること」を聞いても、それはその人の一面でしかないし、それを深掘りするだけじゃ、本質的な信頼関係は築けないんですよ。むしろ、もっと相手の「価値観」や「行動原理」を知るような質問のほうが、意味あるんですよね。
たとえば「なぜそれをやるのか?」とか、「どういうときに一番楽しいと感じるのか?」みたいな、抽象度の高い問いのほうが、相手との距離を縮める上では有効だったりします。「興味を探る質問」ってのは入り口でしかなくて、そこからどう踏み込むかが本当のコミュ力なんですよ。
「会話しない力」の重要性
「話を取らない」って、逆にストレスじゃない?
「相手の話を取らないようにしましょう」っていうのは、まあマナーとしては正しいと思うんですけど、実際の会話って、そんなに綺麗にターン制で進まないんですよね。
むしろ、自然な会話って、ある程度の「かぶせ」や「割り込み」があるからテンポが生まれるわけで、すべての会話を「一人が話し終わるまで待つ」ってやってると、なんか演劇の稽古みたいになるんですよ。
で、「知ってる話題でも『それ知ってる』って言わずに聞きましょう」っていうアドバイスも、確かに共感を優先するには有効かもしれないけど、逆に言うとそれって「嘘をつく」ことにもなり得るわけですよ。
本当に知ってるなら、「それ知ってます、○○ですよね」って言って、そこからさらに話を深めていけばいいだけの話で、なんで「知らないふり」を強要されなきゃいけないのかっていう。結局、「共感」と「嘘」の境界が曖昧になるんですよ。
つまり、相手に気を使いすぎるあまり、自分を抑えすぎると、会話そのものがストレスになる。そうなると、もはやコミュニケーションの目的って何なんですか?って話になるわけで。
「会話しない力」が求められる時代
そもそも、これだけ「テクニック」を積み重ねて、やっと成立するコミュニケーションって、なんか疲れませんか?って話なんですよ。現代って、SNSでも職場でも「話すこと」に疲れてる人が多いわけで、むしろ「会話しない力」が求められてる時代なんですよね。
つまり、無理して会話しなくても成立する関係性とか、沈黙が気まずくない関係とか、そっちのほうが人間関係としてはレベル高いんじゃないかって思うんですよ。
たとえば、長年付き合ってる友人とかって、別にずっと話してなくても平気だったりするじゃないですか。あれって、もう「言葉」じゃなくて「信頼」で成立してる関係性なんですよ。
だから、「話すこと」や「聞くこと」よりも、もっと根底にある「関係性の質」を上げるって方向のほうが、本質的なコミュニケーション能力と言えるんじゃないですかね。
「超コミュ力」が教えてくれないこと
「誰とでも仲良くしよう」は幻想
この本って、「誰とでもうまく話せる方法」みたいなスタンスですけど、要は「万人受けするコミュニケーションの技術」なんですよね。でも、それって結局「八方美人の作法」ってだけで、根本的な人間関係の問題を解決してるわけじゃないんですよ。
本来、人間関係って相性があるし、誰とでも分かり合えるって幻想なんですよ。むしろ、合わない人と無理にコミュニケーション取ろうとすること自体がストレスの元になるわけで。
だから、「すべての人とうまくやろうとしない」っていう前提のほうが、実は健全なんですよね。必要な相手とだけ、深く付き合えばいいし、それ以外は「聞き流すスキル」のほうが大事なんですよ。
「コミュ力」は万能ではない
最後に、「コミュ力さえあれば人生うまくいく」みたいな論調って、ちょっと楽観的すぎるんですよね。現実には、いくらコミュ力が高くても、理不尽な上司はいるし、空気を読まない同僚もいるし、通じ合えない人間は山ほどいるんですよ。
だから、コミュニケーションのスキルを磨くっていうのは、それはそれで価値あることなんだけど、過信しちゃいけないんですよ。「うまく話せばすべてが解決する」ってのは、ちょっとした幻想であって、本当に必要なのは「うまく話せない人ともどう付き合うか」っていう視点なんですよね。
結局、最強のコミュ力って、「距離の取り方を知ってること」なんですよ。話すのが上手いことよりも、「無理せず、自分のペースで人と関われる力」のほうが、人生長く付き合っていくうえでは、よっぽど大事なんじゃないですかね。

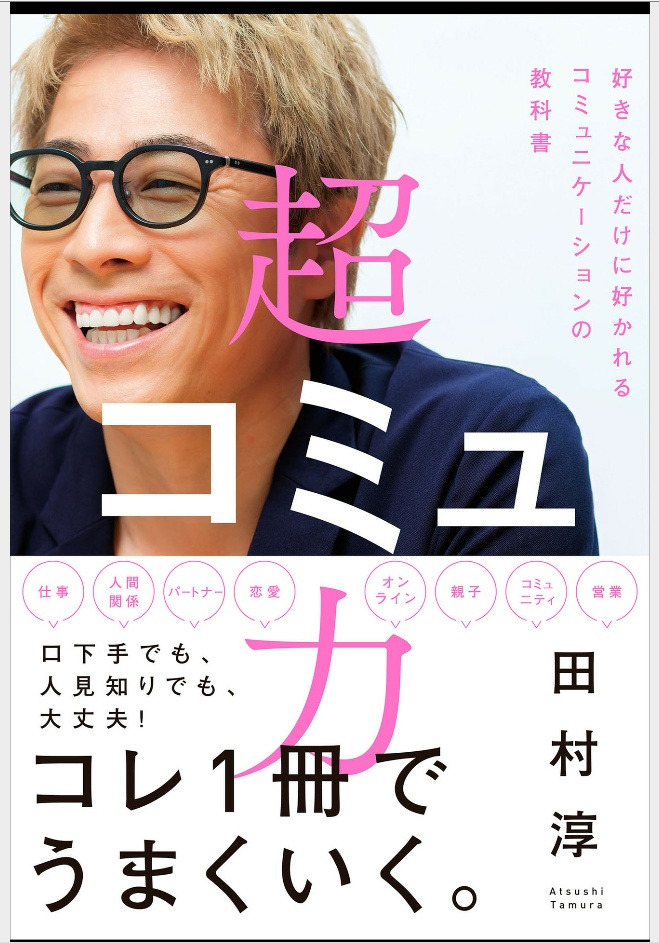


コメント