■働き方の進化と日本の遅れ
◆働き方1.0の「呪い」から抜け出せない国
要はですね、日本って「働き方1.0」にまだどっぷり依存してる国なんですよ。年功序列と終身雇用って、戦後の高度経済成長の時代にはすごく機能してたんですけど、今の時代にはまったく合ってない。にもかかわらず、「安定」とか「会社のために尽くす」みたいな価値観が根深く残っていて、いまだにその幻想を引きずってる人が多いんですよね。
で、「働き方2.0」っていう成果主義的な考え方が入ってきたものの、日本企業ってそれをうまく取り入れられてない。なんか中途半端なんですよ。要は、成果主義っぽく振る舞うけど、評価基準が曖昧で、結局「年功」とか「社内政治」が強かったりする。そりゃ、やる気も出ないし、優秀な人ほど辞めていくわけです。
◆「働き方3.0」や「4.0」は他人事じゃない
でね、働き方3.0とか4.0っていうと、多くの人が「自分には関係ない」とか「特別なスキルが必要」とか言うんですけど、それって思考停止なんですよ。シリコンバレー型のプロジェクトベースの働き方とか、ギグエコノミーってのは、「自分の時間と能力を、どうやって切り売りするか」っていう話で、実は誰にでも応用できるんですよ。
たとえば、クラウドワークスやランサーズみたいなプラットフォームでちょっとしたスキルを活かして収入を得るとか、YouTubeやnoteで情報発信するとか、やろうと思えば誰でもできる時代なんです。つまり、「やるかやらないか」だけの話。
日本人って「完璧じゃないと始めちゃいけない」って思ってる人が多いんですけど、海外だと「まずやってみて、改善すればいいじゃん」ってノリなんですよ。その差がどんどん広がってるのに、自覚がないってのが一番ヤバい。
■キャリアは自己責任の時代へ
◆会社に依存するのは時代遅れ
「キャリアは自己責任」って言葉、ちょっと冷たく聞こえるかもしれないですけど、現実を見れば当たり前の話なんですよ。要は、会社が従業員の人生なんて責任取ってくれないってこと。リストラされたとき、「いや、頑張ったんですけど…」って言っても誰も助けてくれないわけです。
ネットフリックスなんかは、それを徹底してるわけで、「君は今ここで必要ないからクビね。でも転職先は探すの手伝うよ」ってスタンスなんですよ。これが冷酷に見えるかもしれないけど、実は合理的で、逆に「自分の能力で飯を食っていける」って安心感にもなるんです。
だから、会社にぶら下がってるだけの人は、いつ足元をすくわれてもおかしくない。つまり、「会社がなんとかしてくれる」って考え方は、もう通用しないってことですね。
◆専門性を磨くのが最強の保険
で、「じゃあどうすればいいの?」って話になるんですけど、結局は「スキル」なんですよ。自分が何かに特化していて、「この分野なら負けない」って言えるようなスキルがあれば、どこの会社でも通用するし、フリーランスとしてもやっていける。
Googleのエンジニアとか見てるとわかると思うんですけど、優秀な人にはとにかく高い報酬を払うし、会社側も全力で引き留めようとする。それって「成果が出せる人」だからであって、逆に言うと「成果が出せない人」は、どんなに長く働いてても評価されない。そういうシビアな現実に、もっと日本人は向き合うべきなんですよね。
■テクノロジーと働き方の交差点
◆ムーアの法則のインパクトを舐めてはいけない
で、ここで無視できないのがテクノロジーの進化です。ムーアの法則で語られるように、テクノロジーは指数関数的に進化してるわけで、人間の仕事の多くがどんどん機械に置き換わってるんですよ。チェスや囲碁で人間がAIに勝てなくなったように、ホワイトカラーの仕事も確実に自動化されていきます。
つまり、「言われたことをこなすだけ」の人間は、もう必要とされないんです。逆に、「自分で課題を見つけて、解決方法を考えて、実行できる」って人間だけが生き残る。そういう意味で、今の教育とか会社の仕組みって、まったくその準備ができてない。
◆変化を楽しめる人だけが生き残る
で、結局のところ、「変化を楽しめるかどうか」ってのが一番大事なんですよ。変化を嫌う人って、「今のやり方が一番正しい」って思い込んでるんですけど、それって単なる思考停止なんですよね。世の中が変わってるのに、自分だけ変わらないっていうのは、もはや怠慢なんですよ。
ネットフリックスのカルチャーデックにもあるように、「常にベストであり続ける」ことが求められるっていうのは、ある意味で厳しいですけど、同時にものすごくフェアでもあるんですよね。要は、実力さえあれば、年齢も国籍も関係ない。そういう世界で勝負したい人にとっては、今ほど面白い時代ってないと思いますよ。
■エンゲージメントと生産性の不都合な関係
◆「やる気のない会社員」が量産される仕組み
日本の「エンゲージメント指数」が世界でも最低レベルっていうのは、わりと知られてる話ですけど、じゃあ「なんでそうなるの?」って考えると、答えはわりとシンプルで、働いてる人が「自分の仕事が何かの役に立ってる」と感じられてないんですよね。
要は、「やらされ仕事」ばっかりなんです。無意味な会議、意味のない報告書、上司の顔色をうかがうための仕事。そんなことばっかりやってると、「自分の仕事には価値がない」って思っちゃうんですよ。で、それがエンゲージメントの低さ、ひいては生産性の低さにつながってる。
アメリカとかだと、仕事を「自分のミッション」として捉える人が多くて、それが結果にも直結する。でも日本は、「会社の歯車として機能すること」が良しとされる文化だから、自律性が育たないんですよね。
◆「やる気」は構造で作れる
だから、「どうすればやる気が出るのか」って話になると、個人の努力とか根性じゃなくて、結局は「構造」の問題なんですよ。自分で仕事を選べる、自分の裁量で動ける、自分のスキルが反映される、っていう環境があれば、自然とエンゲージメントも上がるんです。
つまり、「エンゲージメントが低いのは従業員のせい」じゃなくて、「そうさせてる組織の責任」なんですよ。で、今の日本の企業文化って、その構造を変えようとしないから、ずーっと同じ問題が続いてるってだけの話です。
■働き方4.0と日本人のジレンマ
◆ギグエコノミーに飛び込めない理由
働き方4.0、つまりフリーエージェント的な働き方って、日本ではまだまだ普及してないんですけど、これもまた「意識の問題」が大きいんですよね。日本人って、「安定してない=不安」って思い込んでる。でも、正社員でもリストラされる時代に、「安定」っていう言葉自体がもう幻想なんですよ。
要は、「いつかクビになるかもしれない不安定な正社員」と、「収入は不安定だけど自分の裁量で動けるフリーランス」って、どっちが本当にリスクが低いのか?って考えると、案外後者のほうが安全なんですよ。なのに、日本人は「会社にいれば安心」と思い込んでる。これはもう、昭和の価値観が化石のように残ってるだけです。
◆副業から始めるのが最適解
で、「フリーランスなんて無理」って人が多いんですけど、それならまず「副業」で始めればいいんですよ。たとえば、夜や週末の時間を使ってブログを書く、動画編集をやる、プログラミングを学ぶ、みたいな感じで、自分のスキルを商品化してみる。
これって、別に特別な才能が必要なわけじゃなくて、「時間の使い方」と「継続する意志」があるかどうかだけなんです。逆に言えば、それすらやらない人が「変化に適応できない」と言ってるわけで、それって単なる言い訳なんですよね。
■グローバル基準で生きる覚悟
◆GAFAに負ける理由は待遇の違い
今、GAFAみたいな外資系企業が日本の優秀な人材をどんどん引き抜いてるんですけど、これって「グローバルスタンダード」が日本に通用しなくなってる証拠でもあるんですよ。要は、日本企業が優秀な人に対して相応の報酬も裁量も与えられてないってこと。
海外では、「成果を出す人にはとことん報いる」って文化があって、それが当たり前なんですよ。でも日本では、「空気を読んで、波風立てずに…」って人が評価される。そりゃ、優秀な人は出て行きますよね。
「グローバル基準で評価される人材になる」ってのは、単に英語が話せるとかじゃなくて、「成果で語れる人」になるってことなんです。そこを理解してないと、どんどん取り残されるだけです。
◆「自分の市場価値」を可視化する努力
あと、「自分の市場価値」ってのをちゃんと認識してる人が少ないんですよね。会社の中で評価されてるからといって、それが外の世界でも通用するとは限らない。むしろ、社内のルールに最適化されすぎて、外に出たらまったく価値がない、ってケースも多い。
だから、自分のスキルが「他の会社や業界でも通用するのか?」ってことを、常に意識しないといけない。そのためには、転職サイトに登録してみるとか、業界の勉強会に参加するとか、そういう「小さなアクション」が必要なんです。
「自分の市場価値が低いまま、会社にしがみつく」っていう状態が一番危険で、そうならないためには、「自分のキャリアは自分で作る」って覚悟が必要なんですよね。
■働き方の未来は「選択」の連続
◆選ばない人が損をする時代
で、最後に一番大事な話をすると、これからの働き方って、「選択の連続」なんですよ。「この会社で働き続けるか?」「副業を始めるか?」「スキルアップに投資するか?」っていう、日々の小さな選択が、5年後、10年後の人生を大きく分ける。
問題は、多くの人が「選ばない」ってことなんですよ。「とりあえず今のままでいいや」とか「失敗したくないから様子見しよう」とか。でも、その「選ばない」という選択こそが、最も大きなリスクなんです。
働き方4.0の世界では、「動いた人だけが得をする」仕組みになってる。だから、何かを選んで動き続けることが、唯一の生存戦略なんですよ。
◆「働かない自由」を手にするために
最後にちょっと皮肉っぽくまとめると、「働き方を変える」っていうのは、実は「働かない自由」を手に入れるための手段でもあるんですよ。どういうことかというと、フリーランスで高単価の案件を取れれば、1ヶ月働いて1ヶ月休むってこともできるわけです。
つまり、選択肢が増えるってこと。だから、今こそ「何のために働くのか?」「自分にとっての自由とは何か?」っていう問いに向き合うタイミングなんですよね。
要は、「働き方を選べない人は、人生も選べない」ってことだと思います。

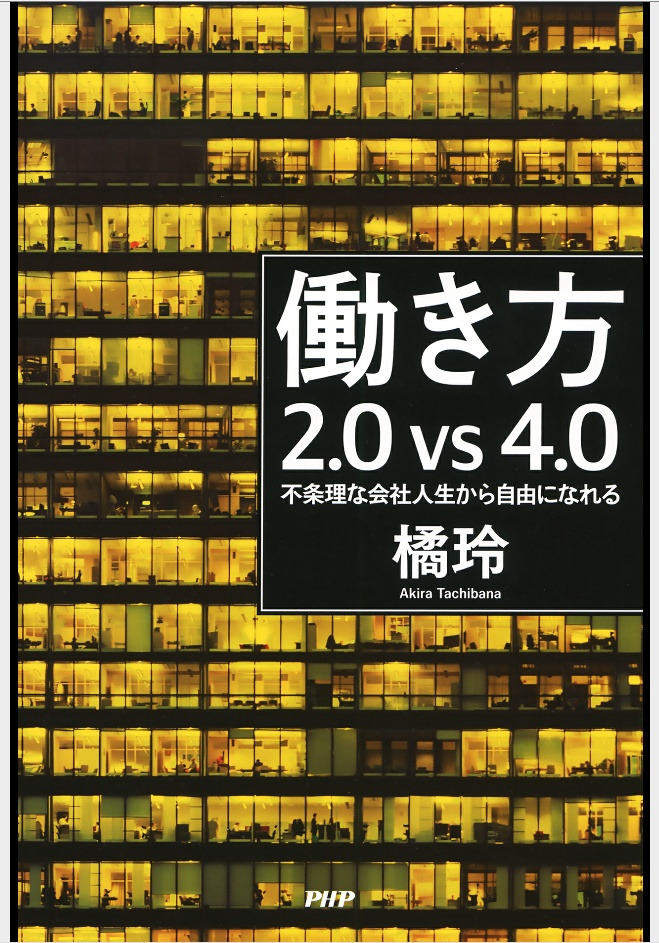


コメント