声のトレーニングに隠れた「不合理」
なぜそこまで細かくこだわるのか?
要はですね、ヴォイストレーニングって、めちゃくちゃ細かく呼吸とか共鳴とか、滑舌とかにこだわるわけですよ。でも、結局それって、どこまで行っても「正解」がない世界なんですよね。 たとえば、アナウンサーが母音と子音をきっちり発音するって話が出てきますけど、じゃあ、世の中にいる人気のある配信者とか、タレントって、必ずしも滑舌が完璧なわけじゃないじゃないですか。 つまり、**「正しい発声」=「成功する声」**とは限らないわけで。 なのに、「こうしなきゃダメだ」と思い込んで何時間もトレーニングしてるとしたら、ちょっと不合理なんですよね。
理想と現実のズレ
深い腹式呼吸ができると、声が安定するって話も、まあ理屈ではそうなんでしょうけど、実際に腹式呼吸を完璧にマスターしてる人ってどれくらいいます? 普通に会社員やってる人が、じゃあナレーション収録で腹式呼吸を毎回意識してるかっていうと、たぶんそんなにいないんですよね。 それでも、別に誰も困ってない。 要は、**「完璧を目指しても社会に求められてない」**ってことなんですよ。 だから、努力の方向性を間違えちゃうと、努力自体が無駄になるんじゃないかなと思ったりします。
結局、才能と相性の話になる
筋肉より耳を鍛えたほうが早い説
筋力を鍛えるとか、柔軟性を高めるとか、すごい大事っぽく書かれてますけど、僕が思うに、声に関して一番重要なのって**耳**なんですよ。 要は、「自分の声をどう聞こえるか」っていう感覚を磨くほうが圧倒的に効率いいんですよね。 録音して聴き返せってアドバイスも書かれてましたけど、そこにもっと注力すればいいと思うんです。 だって、実際に「声がいい」と思われる人って、無意識に声のトーンとかスピードを調整してるわけで。 筋肉ムキムキでも、耳がポンコツだったら、結局意味ないんですよ。
声の良し悪しは市場が決める
あと、共鳴とか滑舌とか、いくら理屈を並べても、結局は聞き手がどう感じるかなんですよね。 つまり、声の世界も、**市場経済**なんですよ。 「この声、好き!」と思われるか、「なんか聞きづらい」と思われるかは、理屈じゃない。 共鳴がうまくいってなくても、愛嬌のある声だったらウケるし、発音が甘くても雰囲気で許される場合もある。 結局、どれだけ正確な技術を持ってるかよりも、**どれだけ市場に刺さる声を持ってるか**がすべてなんですよね。
本質は「続けられるかどうか」だけ
小手先のテクニックより「習慣」
で、細かいテクニックよりも、結局モノをいうのは「続ける力」だったりします。 この本でも、毎日録音しろとか、毎日ストレッチしろとか言ってますけど、実はそこが一番本質なんですよ。 たとえば、腹式呼吸を1日でマスターできる人なんていないわけで、毎日ちょっとずつ意識して、少しずつ積み上げていくしかない。 それを毎日続けられる人が、最終的に声でも仕事が取れる。 だから、「今日から腹式呼吸を完全に習得するぞ!」みたいな意気込みより、**「10年続ける」**くらいの感覚のほうが大事なんですよ。
努力を見せないほうが得する世界
あとね、努力してる感を出すと逆に損する世界でもあるんですよ、声の仕事って。 「こんなに練習しました!」ってアピールする人より、さらっと自然体で声を出せる人のほうが、結果的に評価される。 たとえば、収録現場とかでも、「なんかこの人、余裕あるな」って思われたほうが得なんですよね。 だから、がんばってる自分に酔わないことも、けっこう大事だったりします。 要は、**「努力してないように見える努力」**が最強ってことです。
声の仕事に必要なのは「器用さ」
一つの技術に固執すると失敗する
つまりですね、ヴォイストレーニング大全みたいな本を読むと、「腹式呼吸が大事」「共鳴が大事」みたいに、各パートがものすごく重視されて語られるわけですけど、実際の現場では**全部が中途半端でもなんとかなったりする**んですよね。 たとえば、声量がそこそこだけど滑舌がめちゃくちゃいいとか、逆に滑舌が甘いけど声に妙な色気があるとか。 結局、**一個の欠点を他の魅力でカバーできるかどうか**って話だったりするんですよ。
それなのに、「呼吸だけ」「共鳴だけ」みたいに一個にこだわると、総合力が下がるリスクがあるんですよね。 器用にバランス取りながら、自分の武器を見極める。これが現実の世界では求められるんじゃないかなーと。
理屈よりも「受け手の感覚」優先
たとえば、声の共鳴ポイントを必死に研究した結果、理論上は完璧な声になったとしても、それを聴いた相手が「なんか気持ち悪い」って思ったら終わりなんですよね。 要は、**理屈じゃなくて感覚**なんですよ、結局。 「聞いてて気持ちいい」と思わせたら勝ちだし、「うるさいな」と思わせたら負け。 そこに、どれだけ共鳴が正しいかとか、滑舌が完璧かとか、ほぼ関係ない。 だから、**受け手ファースト**で考える柔軟さのほうが100倍大事だと思うんですよ。
「正しい声」より「売れる声」
完璧を目指すのは自己満足
ヴォイストレーニング大全の内容って、ほんとによくまとまってて、これ全部できたらすごい声になるんだろうなーとは思います。 でも、**完璧な声=売れる声ではない**んですよね。 自己満足で完璧を追い求めるのは悪くないんですけど、商売にするなら**売れることが正義**なんですよ。 だから、「自分の声が商品になるとしたら、何がウリなのか」を冷静に分析するほうが、よっぽど効率的だったりします。 「声の響きがいい」とか「耳障りがいい」とか、相手がどう感じるか。そこだけを突き詰めればいい。
売れない声をどれだけ鍛えても無駄
そもそも、めちゃくちゃ努力して発声を鍛えたとしても、市場にニーズがなかったら意味ないんですよね。 たとえば、昔は「正統派アナウンサー声」って重宝されましたけど、今ってむしろちょっと癖がある声のほうが人気だったりするじゃないですか。 つまり、**市場のニーズに合わせられる柔軟さがないと、どれだけ頑張っても空回りするだけ**。 それに気づかずに、ひたすら「正しい発声」だけを目指してる人って、けっこう損してると思うんですよね。
地味な努力と、偶然のチャンス
積み上げだけでなく「運」も大きい
声の世界って、ものすごく偶然に左右される部分もあるんですよね。 たまたま誰かに声を気に入られて仕事が広がるとか、偶然の出会いでチャンスが生まれるとか。 要は、**地道な積み上げも大事だけど、それだけじゃダメ**。 「偶然に出会ったときにちゃんと拾える力」を持ってるかどうかが、最終的な差になるんです。 だから、毎日コツコツ録音して、声を磨くのも大事だけど、同時に**チャンスを見逃さないアンテナ**を張っておくことも重要。
「声を使った仕事」の多様化
昔は声の仕事って、ナレーターとかアナウンサーとか、かなり限られてましたけど、今はYouTubeもあるし、Vtuberもいるし、個人配信も山ほどあるじゃないですか。 つまり、**声を使ったビジネスモデルが多様化してる**んですよね。 だから、昔ながらの「正統派発声」だけを極めても、あんまり意味がない。 むしろ、「どこで自分の声が刺さるか」を探すほうが大事なんです。 癖のある声でも、演技力がなくても、リスナーが「この声好きだな」って思えば、それで成立する。 要は、**声の仕事=多様性の時代**なんですよ。



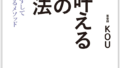
コメント