うん、この本の内容をひろゆき視点で解釈すると、要は「フォロワー数とかの数字を気にしないで、信頼を積み上げることで生き残る方法」って話ですよね。で、ここから考えられるのは、そもそも「なぜ人は数字にこだわるのか」「数字から降りることで本当に得られるものは何か」っていう点です。
数字を追うことの罠と本質
なぜ人は数字を求めるのか?
人間ってわかりやすい指標が好きなんですよ。フォロワー数とか売上とか、数字が増えたら「自分は成功している」と思える。でも、結局それって「数字に支配されてる」ってことなんですよね。 例えば、Twitterでフォロワーを増やすことを目的にすると、「バズるための発言」を優先するようになる。そうすると、本来の自分の意見よりも「受けそうな発言」をするようになって、最終的に誰に向けて発信してるのかわからなくなる。
数字のゲームから降りると何が変わるのか?
この本では「数字を追うのをやめて、人とのつながりを重視しよう」って言ってるんですけど、これってある意味「マイペースに生きろ」って話なんですよね。でも、これを本当に実践するには、「数字に頼らないと生きられない社会構造」から抜け出す必要がある。 例えば、インフルエンサーはフォロワー数が収入に直結するから、数字から降りるなんて無理なんですよ。逆に「仕事の依頼が人づてで来るような環境」を作っている人なら、フォロワー数とか関係なく仕事が回る。つまり、環境をどうデザインするかが重要になってくるわけです。
「ギブの精神」って本当に得なの?
一方的なギブは搾取される
この本では「ギブを続ければ信頼が得られる」と言ってるんですけど、現実はそんなに甘くないですよね。 「与えれば返ってくる」ってのは理想論で、実際には「もらえるものはもらっておこう」って人も多い。特にビジネスの世界だと「無料で価値を提供してくれる人」は便利に使われるだけで終わることもある。 だから、ギブをするにしても「自分にとってメリットがあるギブ」を考えないといけない。例えば、「無料でアドバイスをするとしても、相手が本当にそれを活かせる人かどうかを見極める」とかね。
ギブを続けると「意味のある存在」になれるのか?
この本では「他の誰でもなく、あなたに頼みたいと思われる存在になれ」と言ってるんですけど、これって要は「差別化しろ」ってことなんですよね。 例えば、単に仕事が早いだけのプログラマーだったら、安い人に置き換えられる。でも、「この人に相談すると、プラスアルファのアイデアがもらえる」とか「対応がめちゃくちゃ親切」みたいな要素があると、仕事が切られにくくなる。 結局、「数字を追わない」ってのは、「別の指標で価値を測る仕組みを作る」ってことなんですよね。
「ノールックパス」が成立する環境とは?
そもそも信頼できる人が少ない
本の中では「信頼関係があれば、詳細を確認せずに人を紹介できる」と言ってますけど、これって結局「ちゃんと信頼を積み重ねた人同士の話」なんですよね。 例えば、適当に知り合った人を「この人いいですよ」って紹介して、それが微妙な人だったら、結局自分の信頼も落ちる。だから、本当にノールックパスをやるには、「信頼できる人間関係を作るための土台」が必要になる。
人脈の広さより深さが重要
この本の考え方って「薄いつながりよりも深い信頼を築け」って話なんですけど、これって要は「狭く深く付き合える人を増やせ」ってことなんですよね。 例えば、仕事を頼むときに「安いから適当な人に頼む」ってやると、結局トラブルが起きて余計にコストがかかる。でも「この人なら絶対大丈夫」って信頼できる人がいれば、細かい確認をしなくても仕事がスムーズに進む。 そう考えると、「広く浅いつながりを増やすよりも、深く信頼できる人を増やしたほうが得」ってことになりますよね。
数字に縛られない生き方のリスクと対策
数字を気にしないと「評価されない」問題
「数字を追わない」っていうのは理想としてはいいんですけど、社会って基本的に数字で評価する仕組みになってるんですよね。 例えば、フリーランスのデザイナーが「フォロワー数とか気にしません」って言ったとして、じゃあ企業がその人を選ぶ基準は何か? となると、「過去の実績」か「紹介」くらいしかない。でも実績を見せるにも、フォロワー数が多いほうが「なんとなく信用できる」って思われる。 要は、「数字にこだわらない生き方」をするなら、それに代わる「わかりやすい評価基準」を作らないといけないわけです。例えば、「特定の分野で圧倒的に詳しい」とか「業界の重鎮に評価されてる」とかね。
「評価されなくてもいい」は本当に成立するのか?
この本では「他者とのつながりを重視しよう」と言ってるんですけど、結局のところ、人は何かしらの「評価」を受けないと価値を認めてもらえないんですよね。 例えば、いくら「ギブを続けてます」と言っても、それを評価する人がいなかったら、ただの自己満足で終わる。 だから、「数字を追わない」ことを貫くなら、「自分を評価してくれる相手」をちゃんと見つけることが必要になってくる。そうしないと、ただ「努力はしてるけど報われない人」になっちゃうんですよね。
ギブを続けるための仕組み
ギブし続けるのは意外としんどい
「ギブをし続ければ信頼が得られる」っていう話ですけど、これって裏を返すと「ずっとギブし続けなきゃいけない」ってことなんですよね。 例えば、毎日20通の「GIVEメール」を送るって書いてありますけど、普通に考えてこれめちゃくちゃ大変ですよね。しかも、相手が本当に喜んでるかどうかは分からない。 結局、ギブを継続するには「ギブが自分にとっても負担にならない仕組み」を作るのが重要なんですよ。例えば、「自分の好きなことの延長でギブできる仕組みを作る」とかね。
ギブを利用されないための線引き
ギブをしすぎると「この人は無料で助けてくれる人」と思われる可能性があるんですよね。 例えば、ビジネスの場面だと「この人に聞けばタダで情報をもらえる」って思われた瞬間に、ただの便利屋になっちゃう。 だから、ギブをするにしても「どこまでが無料で、どこからが有料か」を明確にしないといけない。例えば、ちょっとしたアドバイスなら無料だけど、具体的なプランを作るのは有料とかね。 ギブの精神は大事ですけど、「自分の価値を安売りしない」ことも同じくらい大事なわけです。
「ノールックパス」の落とし穴
ノールックパスが成立するのは「同じ価値観の人」だけ
この本では「信頼があれば、確認せずに人を紹介できる」と言ってますけど、これは「信頼できる人同士のネットワーク」が前提なんですよね。 例えば、全く価値観の違う人にノールックパスをやると、「なんでこんな人紹介したの?」ってなって、逆に信用を失うこともある。 だから、ノールックパスを成立させるには、「価値観の合う人とのネットワークを作ること」が必要になってくる。そうしないと、単に「適当な紹介をする人」になっちゃいますよね。
紹介が増えると「関係が薄まる」リスク
ノールックパスの問題は、紹介が増えると「関係性がどんどん薄まる」ことなんですよね。 例えば、「あの人、めっちゃ人を紹介してくれるけど、実際にはそこまで深く知らない人ばっかりじゃん」って思われると、結局信頼を失うことになる。 だから、ノールックパスを使うにしても、「本当に信頼できる人だけを紹介する」とか「ちゃんと自分のフィルターを通す」とか、何かしらのルールを作らないと、ただの適当な仲介屋になっちゃうんですよね。
本当に「数字から降りる」ことは可能なのか?
結局、数字は避けられない
「数字から降りる」と言っても、実際には「違う形で評価される仕組みを作る」だけの話なんですよね。 例えば、フォロワー数を気にしない代わりに、「誰が自分のことを評価してくれるか」を気にするようになる。結局のところ、数字じゃなくても「評価の指標」は必要になるんですよ。 だから、「数字に縛られない生き方」をするなら、「数字以外の指標をどう作るか」が重要になってくる。
最終的には「環境」がすべて
この本の内容を突き詰めると、「結局、環境をどう作るかが重要」ってことなんですよね。 例えば、「数字に縛られずに生きる」って言っても、それが許される環境を作らないと意味がない。 会社に勤めてるなら、上司が「数字を見ない評価」をしてくれないと厳しいし、フリーランスなら「数字を気にしなくても仕事が来る仕組み」を作る必要がある。 結局のところ、「数字を追わない」ことができるかどうかは、「どんな環境を作るか」にかかってるわけです。

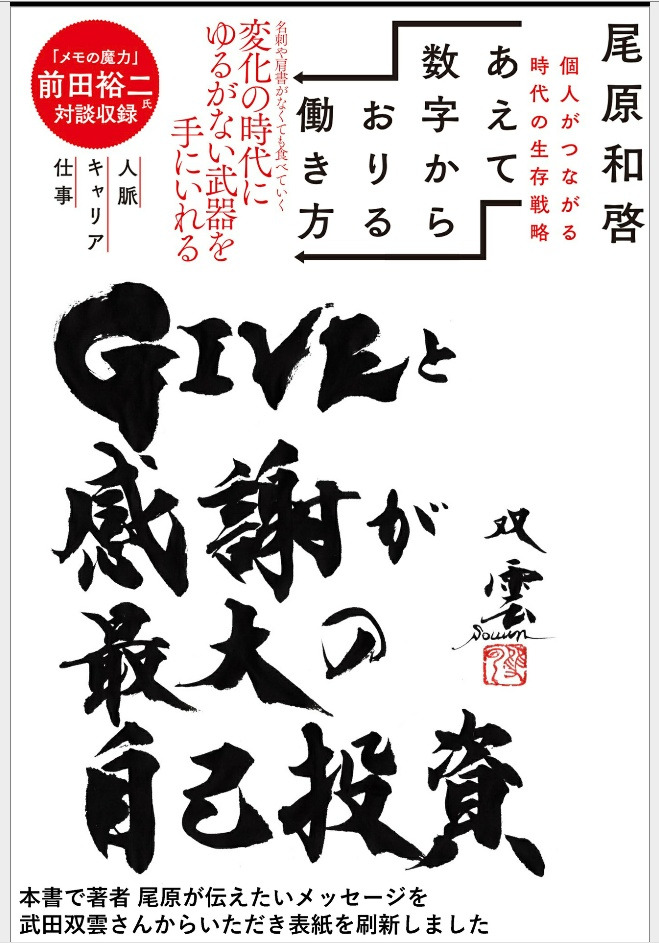
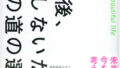

コメント